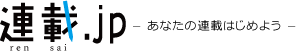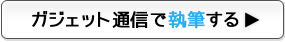ウチこそ、タコ焼きの元祖、という店がいくつかある。じゃあ、なんでタコが入ってるのか、ちゃんと説明してみせろよ。博物館で当時の現物まで抑えたわけじゃないが、おおよその道筋はわかった。その謎を解く鍵は、あの丸い凹みの焼き器にある。じつは、あれ、驚いたことに、アジアからヨーロッパ、カナダまで、世界中にあるのだ。
話は、十三世紀のタイから始まる。スコータイ朝第三代ラームカムヘーン大王が、中国から陶工たちを招聘した。それまでタイでは水の滲みる素焼の土器しかできなかったのだが、この華人陶工たちによって釉薬が持ち込まれ、宋胡禄として、タイの一大輸出産品となった。また、タイでは、昔からカノムコック(米粉のココナッツミルク焼き)が甘い菓子として好まれていたが、これを作るのに、いちいちバナナの葉で小分けしていた。それが、釉薬の登場によって、多穴の陶器パンに取って代わる。これこそ、まさに、あのタコ焼き器の大元。
話はまだ続く。これが直接に日本に入ってきたのなら、山田長政の時代から日本に同じようなものがあっただろう。だが、日本に米粉はあってもココナッツミルクは無く、カノムコックのようなふんわりとした焼き菓子を作ることはできなかった。だから、そのための多穴陶器パンも必要がなかった。だいいち、カノムコックに、なんの具も入ってはいない。
まさにその山田長政のころ、オランダもまたタイに入り込んでいた。が、1663年に華僑たちと貿易を争い、追放されてしまう。この後、ヨーロッパでオランダ打倒をもくろむルイ十四世のフランスがタイに取り入る。しかし、これもカトリックの宣教がしつこく、十七世紀末には追放されてしまった。このとき連中がヨーロッパに持ち帰ったのが、あの多穴陶器パン。
オランダには米粉が無いので、小麦粉と蕎麦粉で代用した。これが、お菓子のポッフェルチェ。そのパンは、その後、鋳物の鉄板で大型化し、デンマークからカナダまで、爆発的に普及する。クリスマスシーズンには、各地のマーケットにポッフェルチェの屋台が出る。ドイツやオランダなんかでは、日本のタコ焼き器そっくりの家庭用ポッフェルチェ焼き器がふつうにそこらで売っている。
一方、帰国したフランスの宣教師たちは、この多穴陶器パンをエスカルゴの調理に使った。エスカルゴは、修道院の葡萄畑で養殖されており、復活祭前の肉断ちの季節に好んで食べられていた。エスカルゴと言うと、殻ごとのイメージがあるが、あれは、いったん全部を引き出し、寄生虫の危険性がある内臓を取り去って味付けし、また殻に詰め直したもの。当時は、掃除した身だけを多穴陶器パンで直接に香草バター焼きにしていたようだ。
さて、明治維新。長崎の浦上天主堂を始めとして、日本にも大勢のフランス人カトリック宣教師たちがやってくる。1900年ころになると、神戸にも、フランス人やオランダ人は大勢いた。連中が作ったのが、エスカルゴのベニエ。じつは、エスカルゴ料理では、殻を使ったブルゴーニュ風の香草バター焼きだけでなく、ポッフェルチェに似たベニエ(衣揚げ)も一般的な調理方法だ。日本人でも御相伴にあずかった者たちがいただろうが、その具がまさかカタツムリとは思うまい。いや、たとえその正体を教えられたとしても、その寄生虫の危険性についても、伝えられただろう。それで、タコだ。
つまり、タコ焼きのタコは、もともとはエスカルゴ。第一次世界大戦中の1918年、なんらかの事情で在留外国人から例の鉄板を譲り受けた関西の露天商の金城組(現・三島屋)が、オランダ風のポッフェルチェを「ベビーカステラ(鈴カステラ)」として日本で最初に売り出している。そして、翌1919年、明石の向井清太郎が、エスカルゴまがいのタコが入った「玉子焼き」を始めた。昭和に入ってからの大阪のラジオ焼きなんかより、はるかに古い。ちなみに、日本で最初に日本人にエスカルゴを出したのは、まさに神戸の「エスカルゴ」というフランス料理のレストラン。ただし、それも、1953年、つまり、戦後になってからのことだ。そして、タコ焼きは、日本食ブームとともにアジアに再輸出。タイではあまりタコを食べないので、カニカマが入っているとか。
by Univ.-Prof.Dr. Teruaki Georges Sumioka 純丘曜彰教授博士 (大阪芸術大学芸術学部哲学教授、東京大学卒、文学修士(東京大学)、美術博士(東京藝術大学)、元テレビ朝日報道局『朝まで生テレビ!』ブレイン。専門は哲学、メディア文化論。
オフィシャルサイト http://www.hi-ho.ne.jp/sumioka-info/
生活の哲学 http://sumioka.doorblog.jp
ニュースの蜂 http://newsbee.doorblog.jp)