
[出典:「自衛隊を活かす:21世紀の憲法と防衛を考える会」(2024年2月29日)]
【要旨】
戦争を始めることは容易いが、終わらせるには実に困難が伴う。2022年2月24日から始まった「ロシアのウクライナ侵攻」と2023年10月7日に再び奇襲したハマスとイスラエルの軍事衝突が続くパレスチナ情勢。この間、世界でウクライナやパレスチナに連帯する運動や反対の声を上げる市民を世界政府レベルで「言論弾圧」する動きが波及している。今起きているウクライナ戦争を終わらせるには「本物の『国際世論』の力を与える新たな『秩序観』を人類が作ることだ」と「自衛隊を活かす会」の柳澤協二代表は指南する。また10.7と呼称されるガザ危機を終焉に向かわせる「『停戦』と『終戦』は明確に違う」と定義する東京外国語大学の伊勢崎賢治名誉教授は、その先の「国際社会からの復興支援の『受け皿』となるガザの行政機構をいかに構築するか?日本には『平和外交』の確かな実績がある」と豪語する。フィリピン政府と同国南部ミンダナオ島の反政府武装勢力モロ・イスラム解放戦線(MILF)が、2016年にイスラム系住民らによる新たな自治政府設立を目指す和平工作を『国際開発機構(JICA)』故・緒方貞子理事長が先頭に立って主導したのだ。
翻って今般、岸田政権下の「安保関連三文書」で「次期戦闘機」の日英伊共同開発を国産で可能にする法整備をしてしまい日本は「軍拡」への道を突き進む。「武器取引反対ネットワーク(NAJAT)」の杉原浩司代表は「防衛装備移転三原則」議論の中で「殺傷武器は外す」という決断を当時の軍縮大使がしなかったことが大きく影響し「人道的軍縮キャンペーン」が有効に関与できない「歯止め」が効かない現実を深刻視する。スウェーデンの環境保護活動家グレタ・トゥーンベリ氏が「全ての人々が声をあげていくことに責任がある。『静寂』を通すことはイスラエルの占領と大量殺戮の共犯者に等しいことになってしまうからだ。目前で展開されていく『ジェノサイド』に中立の立場は存在しない。この許し難い暴挙を終焉に導くことを要求していく」との声を上げただけで欧米政府レベルで「非戦」の口を封じられる。
「宗教的少数派」と「表現の自由」の狭間にある緊迫感―それは「表現の自由」が「攻撃の権利」を含むという問題だ。「言論弾圧」と言えば、2015年1月7日に起きた仏週刊新聞社「シャルリー・エブド」襲撃テロ事件後に「私たちは一体何者なのか?」西洋社会での自分達のアイデンティティーを自問自答した。欧州の中の「反ユダヤ主義」と「イスラム嫌い」が醸成する「ヘイトスピーチ」の空気の中で、ユダヤ人の「人格権」はドイツ憲法「ドイツ連邦共和国基本法」によって保護され、ナチスによるユダヤ人の迫害は彼らのアイデンティティとなっており、ホロコーストを否定することは、その根本のアイデンティティの否定を意味することになる。欧州における刑法の「ヘイトスピーチ禁止法」では攻撃に晒されている人々を保護することを想定していない。むしろ人々の暴行に対する尊厳を守る目的に資するべきだ。
ドイツでは「国際刑法法典」第6条第1項に定義された行為を公共の治安を害しうる仕方で承認し、否定し又は無害化した場合には5年以下の禁固刑に処される場合がある。対象とされているのは特定の民族的、人種的ないし宗教的集団を破壊する目的で行われる「ジェノサイド」であり、これによって公の場におけるホロコーストの否定も禁止されることになる。
ドイツの「民衆煽動罪」の規定を定めた、「ドイツ刑法典」第130条第1項や同条第2項第1号などから、同法典は侮辱にも名誉毀損にも刑罰を加えており、判例によればこれらの禁止は「民族的」「人種的」ないし「宗教的な少数者集団」に対する「侮辱」や「名誉毀損」にも適用されるとしている。これによるユダヤ人に対する「集団的侮辱」や「集団的誹謗」は処罰が可能である。
そのような「言論弾圧」と権力の「ヒミツ」が横行したら…それこそが忍び寄る「軍靴の足音」が聞こえる前兆なのだ。2013年「特定秘密保護法」2014年「集団的自衛権」閣議決定、2015年「安保法制」。安倍政権との闘いの後に岸田政権で打ち出された「安保関連三文書」。日本には国宝「憲法9条」があっても実質的に既に「戦争加担国」でさらなる「軍拡」へ暴走している。その「歯止め」となる「言論の自由の力」を伝えることこそが「『非戦』の国際世論」を高め、このまま日本人が海外の戦争リスクに巻き込まれていかないよう筆者は「平和へ続く国民的議論」を深めることで最大の暴力である戦争に楔を打つ一介の書き手でありたい。
******************************************************************
【要旨】
<リード>
【1】飢餓に苦しむガザ市民 零下の厳冬と安全な飲み水なく困窮するウクライナ
【2】「停戦」と「終戦」は明確に違う
【3】本物の「国際世論」の力を与える新たな「秩序観」を人類が作ることがウクライナ戦争終焉への道
【4】許すな!世界でパレスチナに連帯する運動や言論を欧米など政府レベルで弾圧
【5】国際社会からの復興支援の「受け皿」となるガザの行政機構をいかに構築するか?日本には「平和外交」の確かな実績がある
【6】「殺傷武器は外す」という決断のなさこそ「人道的軍縮キャンペーン」が有効に関与できないワケ
<結び>「言論弾圧」と「ヒミツ」が横行したら…「軍靴の音」がする前触れ
******************************************************************
2024年2月29日、都内某所で「自衛隊を活かす:21世紀の憲法と防衛を考える会(以下、「自衛隊を活かす会」)」が主催する「戦争はどうすれば終わるか ウクライナ、ガザと非戦の安全保障論」出版記念シンポジウムが行われた。
同会が焦点を当てているのは、昨今のウクライナやガザで起きている「戦争をいかに終焉へと導くか?」だ。各パネリストである有識者2名の議論を紹介する前に、しばし、各戦地の最新情勢を押さえておこう。
【1】飢餓に苦しむガザ市民 零下の厳冬と安全な飲み水なく困窮するウクライナ
パレスチナ自治区ガザ地区でイスラエルが続けている戦闘は「ジェノサイド(集団虐殺)」にあたるとし、南アフリカが戦闘停止などを求めた訴訟を巡ってオランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)が2024年1月26日にイスラエル側に「ジェノサイド防止」や「人道状況の改善」を求める「仮保全措置命令」を出した。同年2月26日でその「集団虐殺防止暫定命令」の履行期限を迎えた。
また、翌2月27日には「国連安保理決議2417」(2018年)を踏襲し、国連の議場で国連人道問題調整事務所(OCHA)のラメシュ・ラジャシンハム調停局長が「ガザの総人口576,000のうち4分の1に該当する220万人が深刻な食糧飢饉に晒されている。世界規模で見てもかつてないほどの食糧不安のレベルに人々は直面しているのだ」と訴えた。その上で「このように紛争による飢餓と幅広く波及していく食糧不安によって武力衝突が起きるという由々しき事態にある」しかしながら食糧安全保障の専門家は「(今年)5月までにはガザ北部で完全に農業は崩壊してしまうだろう。もしこの状況が持続するとしたら、損害を受けたり破壊されたり、アクセスできない畑や生産的資産という影響が伴う。多くの人は避難命令や繰り返される追放によって生産的農場を放棄するしかほとんど選択権がない状況にある」と警告する。
[出典:OCHA: Mr. Ramesh Rajasingham updating the Security Council on food security risks in Gaza (27 Feb. 2024)]
他方、ウクライナでは各地でマイナス零下の「厳冬」を迎え、エネルギー施設に影響を及ぼすほどの空爆の結果として、数千もの人々が電気やヒーターを含む重要なサービスもないままウクライナの地を離れる者たちが続出している。
OCHA管轄下の「国連ウクライナ人権監視ミッション(HRMMU)」のデニス・ブラウン人道支援調整官は強く非難。
「2022年2月24日から2024年1月31日までの戦災犠牲者統計として、ウクライナ全土でほぼ1万500人の民間人が殺害され、2万人近い負傷者を出した。うち、580人近くが殺害された子どもで、負傷した子どもは1300人だった」
ウクライナのエネルギー省によれば、エネルギー施設に重大な損害をもたらされたことにより、人々の暖を取る手段を著しく妨げる潜在的な結果を招いている。自治体当局は緩和ケアホスピタルから逃げるように指示。2月13日には6校の子どもたちがオンライン授業に切り替え教育妨害を乗り越えようと試みている。ドニプロペトロフスク州では水分供給がなく、電気供給も機能していない。ヒーターはヘルソン市で一時的に妨害を受けた。2月15日には空爆の余波でリヴィウ州とハルキウ州で電力供給にも障害が及んでいる。
空爆を受けたハルキウ州では水分と下水インフラに損害をもたらされ、人々の水や衛生、保健へのアクセスに著しい妨げが起きた。そのためリヴィウでのNGO「ロカダ」や人道支援組織の「プロリスカ」を含むエイドワーカーらが「小規模な集団感染(クラスター)」の押さえ込みを図っている。
国際NGO「サマリタンズ・パース(Samaritan’s Purse)」はウクライナのシベルスク共同体で水分浄化(濾過)施設を設置する人道支援を行っている。またUNICEFもセリダヴ病院から避難してきた人々のために安全な飲み水を提供している。
[出典:OCHA UKRAINE Winter Attacks : Humanitarian Impact of Intensified Strikes and Hostilities- Flash Update #6 (16 Feb. 2024)]
[出典:Installing Water Purification Systems in Ukraine<YouTube>]
【2】「停戦」と「終戦」は明確に違う
東京外国語大学の伊勢崎賢治名誉教授は「停戦と終戦を混同する人たちがいる。この2つは明確に違う。『停戦』とはむしろ悲劇的な終戦を回避するための『政治工作』のこと。愛国主義もしくは現代では自由と民主主義のためだという『正義』の大義。侵略者に対する憎悪の感情。それらを一時的に抑えて人命の損失と破壊を最小限に抑えるために行われる政治工作を『停戦』と言う」と定義づける。[出典:2023年4月24日ウクライナに今こそ停戦を呼びかける記者会見]
【3】本物の「国際世論」の力を与える新たな「秩序観」を人類が作ることがウクライナ戦争終焉への道

[出典:「自衛隊を活かす会」柳澤協二 代表]
「自衛隊を活かす会」の柳澤協二代表はロシアのウクライナ侵攻した2年前からなおも続く戦争について考察する。
「ウクライナのように陸土の上でお互いの力が拮抗している限り、夥しい犠牲者ばかりを出す戦争になることは避けられない。だが拮抗しているとはいえロシアは核保有大国で、ウクライナはそれほどの軍事大国ではなかった。現にウクライナ本国で使用されている兵器システムや投入できる軍事力を欧米が供与したことで、ロシアと競り合えるまで強靱になった。2023年8月にフランスのエマニュエル・マクロン大統領が『我々はウクライナの敗北を受け入れないし、ロシアの崩壊も望まない』と発言した。まさにこの戦争を取り巻く世界の現実を示したものであろう。もし戦争を終わらせることが最大目的ならば、ウクライナへの武器供与を止めてロシアが勝つことにするところを果たしてそれで本当に良いのか?という疑問符がつく。」
柳澤氏はウクライナ戦争の終焉の前に立ちはだかる障壁を憂う。「昨年末から様々な『停戦案』が出ておりウクライナが譲歩せざるを得ない状況になりつつある。しかして『停戦』になったところで『一時休止』であって『平和』を意味するものではない。お互いに納得できる『和解』がなければならず両国の顔を立てる妥協点をいかに見出すかが非常に困難だ。仮に『譲歩』するとしても、その『代償』をどう補うのか?といえば、国民感情からいっても戦争犯罪の処罰や賠償の問題など昔ながらの戦争の後始末という問題がのしかかってくるのだろう。今、『国際刑事裁判所(ICC)』はロシアのウラジミール・プーチン大統領に逮捕状を出している。プーチン氏がいなくなれば終戦に至るが、現状ロシアをコントロールできるのは同じくプーチン氏だけだ。それ故現実には逮捕できず、『綱渡り』のようなバランス感覚が求められている。」
「我々がもっと戦争の問題を自分事として考えていくには、まさにかつてフランスのジョルジュ・クレマンソー首相が残した名言『戦争というのは『軍人』に任せておくにはあまりに重大なビジネスだ』があるが、今や『戦争というのは『政治家』に任せておくにはあまりに重大なビジネスだ』と言わざるを得ない。それほど政治家というアクターが今日、重大な要素を占めていると思う」とした上で、「国民が戦争というものを『リアリティ』を持って捉えるには、なんとか戦争を避けるという知恵を考えて行かなければならない時代になった。」とした上で、「昨年の国連総会の一般演説でウクライナのウォロディミフ・ゼレンスキー大統領が『大国の拒否権を国連総会の4分の3の多数で覆せるような制度の導入』を訴えたが、私はゼレンスキー氏の提案を支持する。大国の都合ではない、より本物の真っ当な国際世論の力を与えるような新たな秩序観というものを人類が作っていかなければならない。」しかして叡智を絞っても「今年2月末にもゼレンスキー氏はサウジアラビアを訪問したが、サウジアラビアは2023年に40カ国の代表を集めてウクライナ和平会議を主催している。新たな戦争の時代に戻ってしまうのではという危機感を抱いている」と予断を許さない状況にあることを柳澤氏は改めて強調した。
【4】許すな!世界でパレスチナに連帯する運動や言論を欧米など政府レベルで弾圧

[出典:筆者コラージュ作成]
柳澤氏は「終戦に導くには『国際世論』の高まりが重要だ」と予てから繰り返し述べてきている。
件のテーマで今現実に起きていることを別途・他ウェビナーにおける「武器取引反対ネットワーク(NAJAT)」の杉原浩司代表の発言から紹介したい。
「『イスラエル・パレスチナ危機』に対し、スウェーデンの環境保護活動家グレタ・トゥーンベリさんがプラカードを掲げて『ジェノサイドだ』と批判した。これを契機にドイツの『フライデーズ・フォー・フューチャー(FFF)』という気候変動危機に声をあげてきた団体がグレタさんの行動を問題視し、『私たちとグレタさんとは、もはや何の関係もない』という宣言をした。この期間、米国や欧州(独・英など)でも、パレスチナに連帯する運動や言論などを弾圧したり圧力をかけたりということを政府レベルで行なってきた動きが激しくなってきている。そのような空気の中でNGOや市民運動も、ある意味そこに連なる形でパレスチナに連帯する声を抑圧していく。そうした構図が『気候危機運動』の間にも見えてきている。」
著者が目を通した「The Guardian」紙(5 Dec. 2023)によれば、国際NGO「Oxfam」は先頭に立ってイスラエルの「兵器としての飢餓」の悪用を追及してきた。
若者による「気候正義」の運動によって作られたガザについての非合法化した声明とは、多くの主張とは対照的だった。『フライデーズ・フォー・フューチャー(FFF)』は『過激化して』いないし、『政治的になって』もいない。私たちは常に政治的だ。なぜなら私たちは常に正義のために運動してきたからである。パレスチナ人と連帯する立場を表明し、全てが民間人に影響を及ぼすことには疑いの余地はない。
「気候正義」のための政策提言は根本的に人間の人権に配慮する場所からくるものだ。疎外された集団―例えばクルド人やウクライナ人、サーメ語で「サプミ」と呼ばれるスカンジナビア半島北部を中心にトナカイ放牧で生活する少数先住民族や多くの他の場所で―そして彼らは帝国主義や弾圧に抵抗して正義のために葛藤している。私たちのパレスチナとの連帯にはなんの違いもなく、パレスチナ人が昨今直面している人間としての懊悩を恐るべきことから抜け出せるように焦点を移すことを大衆にさせているのだ。
このガザで行われている「ジェノサイド」は、自衛でもなく、いずれにしても相応の反応でもない。数10年に及ぶ窒息するような抑圧のもとで暮らしてきたパレスチナ人の幅広い生き字引きの中からそれもまた無視されることはできない。しかし国際人権NGO「アムネスティー・インターナショナル」は「アパルトヘイト体制」として定義づけている。この間、これだけが全ての状況に関する動機になり得る。スウェーデンの運動として、我々もまたイスラエル武器産業とのスウェーデン軍事協力に責任の一端があると声をあげていかなければならない。
私たちは今、「反ユダヤ人主義的」で「イスラム嫌い」の声明が急増する現状を目にしている。スウェーデンでの活動やヘイトクライム他、世界にも波及しているのだ。スウェーデン国内でも極右スウェーデン民主党のジミー・オーケーソン党首は最近になってモスクを取り壊したが、これに反発したデモ抗議者たちがイスラエル旗を燃やした。「シナゴーグ」の前線に近いスウェーデン最南部のスコーネ地方にある都市マルメで。
「全ての人々が声をあげていくことに責任が生じる。さもなければ静寂を通すことはイスラエルの占領と大量殺戮の共犯者に等しいことになってしまうからである。目の前で展開されていく「ジェノサイド」に中立の立場は存在しない。この許し難い暴挙を終焉に導くことを要求していく」
上述のように、グレタ・トゥーンベリさんが彼女の「Instagram」アカウントに上記の大よその趣旨を投稿するや否や、反応があった。アリエ・シャルズ・シャリカール(Arye Sharuz Shalicar)というイスラエル軍の広報官が「POLITICO」(20 Dec. 2023)に語ったところによると、「誰もがグレタさんとその未来に向けた手段を同一視しているか。私の見解では『グレタ氏はテロリスト支持者』に見える」と。シャリカール氏はまた付言した。「グレタ氏がしていることは今やガザとの連帯を示すものであり、その間にもイスラエルの大虐殺について何も言及がない。それが意味するものとは彼女は実際パレスチナ人美贔屓ではないが、それがさも存在しないようにテーブルの下でパレスチナ人かハマスとイスラム・ジハードのテロ行為を掃討しようとしているようだ」と揶揄した。
しかし後日、シャリカール氏は「このコメントは個人の見解を反映したものではなく、イスラエル国防軍の公式見解でもなかった」と謝罪している。
前出のグレタさんの身に起きた「言論弾圧」の報道を聞き、著者はすぐにある事件を思い起こした。
「Je suis Charlie」連帯、結束そして力。それは仏週刊新聞社「シャルリー・エブド」襲撃テロ事件後に掲げられた「スローガン」だ。
2015年1月7日にパリに拠点を置く同社のWEBサイトが攻撃されたことで SNS上に「同情的な感情や襲撃による犠牲者を支える言説」が溢れた。
事件発生の際、フランスのフランソワ・オランド大統領(当時)は「例外的な蛮行」だと糾弾した。
私たちは自由の国に暮らしているから脅威に晒された。その脅威を中立化し侵略者には処罰を与えるだろう。誰しも共和国の原則と比較した方法で同国で起きた事件を考えるべきではない。宗教的感性と信教の自由、信念を「表現の自由」の潜在的限界性に関して同様に関係づけて新聞社を攻撃したという気付きがあった。そしてそれは暫定的な政策と大衆の生活の中に急速にトップストーリーとして普及していった。事件後の西洋人の感情というものは少数が目立ち、幾らかの反映に値するものだった。まず第一に「私たちは一体何者なのか?」西側、西洋社会での自分達のアイデンティティーというものについて考えた時、私たちはしばしば「白人階級、世俗主義、リベラル」で最も男性的な観念が支配的である。その時、「宗教的他者」とはしばしば良く機能しているリベラル・デモクラシーにとって「脅威」だと考えられてきた。その中でも「表現の自由」のそれが非常にしばしばその柱として言われてきたのである。しかしながらそこには「表現の自由」が伴うからこそ重要な合意に至らない状況が続き、増え続ける宗教性の文脈では「表現の自由」が合理的に置き換わること自体、限界はあっても可能だったという。 「表現の自由」の議論に適用された時には特に攻撃のその性質と原因が水面下で進んでいる調査のように思えた。このことから「宗教的共同体」の見通しか、公的な理由の見込みからいかに行動すべきか。そして民主政治の中の市民の大半によって何が合理的に期待され得るだろうかを考えるべきだ。
だが、「宗教的少数派」と「表現の自由」の狭間にある緊迫感は最初の疑問だ。犯罪を犯したものに対して立ち上がってきたのか?と。この議論は際限なくほぼ無限に広がる。疑問や見解を積み重ねていく中で何年もの時をかけて劇的に移行してきた。一部は結果的に個人間に見て取れるミクロレベルに関する場合。もう一つは幅広い社会や集団、共同体の属性から移行するものだ。ここから私たちが学べることは多い。宗教的少数派と「言論の自由」の関係性の中に潜む攻撃にアプローチしていく中でいかに考察するかという「テーゼ」が浮かぶ。
始まりは実際に何が犯罪を犯すことを考察する一助となるか?多くの学者たちが見解を表明してきた。それは「表現の自由」が「攻撃の権利」を含むという点だ。しかしこの権利は他の人々の尊厳や社会的地位のために敬意を払って実行されてきたものだ。それも屈辱と攻撃の狭間の重要な区別がつけられるとジェレミー・ワルドロン氏は議論する。刑法における「ヘイトスピーチ禁止法」では攻撃に晒されている人々を保護することは想定されていない。むしろ人々の暴行に対する尊厳を守る目的に資するべきだと主訴する。
[出典:”A story of oppression: freedom of expression, minorities, sexual harassment law and offence” <The Religion Factor>University of groningen]
欧州諸国の多くでは「ヘイトスピーチ」は刑罰によって禁止されている。「人種差別撤廃条約」も同様に刑事処罰を求めている。「自由権規約B」も「表現の自由」を保障しているが、個人の名誉のための制約は明示的に認められていることから同述である。
ドイツでは「国際刑法法典」第6条第1項に定義された行為を公共の治安を害しうる仕方で承認し、否定し又は無害化した場合には5年以下の禁固刑に処される場合がある。対象とされているのは特定の民族的、人種的ないし宗教的集団を破壊する目的で行われる「ジェノサイド」であり、これによって公の場におけるホロコーストの否定も禁止されることになる。
ドイツの「民衆煽動罪」の規定を定めた、「ドイツ刑法典」第130条第1項や同条第2項第1号などから、同法典は侮辱にも名誉毀損にも刑罰を加えており、判例によればこれらの禁止は「民族的」「人種的」ないし「宗教的な少数者集団」に対する「侮辱」や「名誉毀損」にも適用されるとしている。
ユダヤ人に対する集団的侮辱や集団的誹謗はこれにより処罰が可能である。ドイツ憲法である「ドイツ連邦共和国基本法」第5条 (1)でも「意見表明の自由」と「情報の自由」、「報道の自由」を保障しているが、「ドイツ連邦憲法裁判所」は「民衆煽動罪規定」の合憲性を支持している。
ユダヤ人の「人格権」は基本法によって保護され、ナチスによるユダヤ人の迫害は彼らのアイデンティティとなっており、ホロコーストを否定することは、その根本のアイデンティティの否定を意味することになるのだ。
[出典:「インターネットの憲法学 新版」松井茂記 著<岩波書店>]
しかるに「ヘイトスピーチ」と「表現の自由」の関係性の中での攻撃は、よりしばしばその集団と集団のアイデンティティーとで取引される。もし私たちが攻撃性を実際の経験である攻撃性とするなら、その代わりにいかなる理由が攻撃性に走らせる構成要件を生むのかを考察する。
換言すれば、差別と定義付けられた人々の尊厳を侵害する「実害」やセクハラの中で利用されることは、新たな又は「自由な言論」と「宗教的感性」に敬意を払って調整された合法的枠組みのための論理的基本から成り得るものだ。
私たちならば、ここに西洋の中のイスラム共同体が脆弱な「文化的アイデンティティー」を確立することができる。多くの西洋諸国におけるイスラム嫌いが今日の西洋社会における「レイシズム」の土壌を支配的なものにした。私たちが、西洋の公共領域の中でイスラム共同体にとっての脆弱な文化的アイデンティティーの完全性という概念を適用したとするなら、何が変わっただろうか?
まず第一に、脆弱な少数派に対する攻撃的な表現の可能な限りの影響力をより理解しやすく提供したことが挙げられる。
次にムハンマドの描いた風刺画の刊行の後、感じてきた攻撃性に反映されているが、その攻撃とは「集団被害」と同様だと考えられている。そう考えること自体が集団被害の経験された「差別的被害」に関するより多くの目覚めを生む一助になり得てきた。
さらにそれは公開討論の中の幅広い緊張感の根底にある、より良い理解ができるようにする。またそれが会話と議論のために必要な空間を生み出すことさえできる機会を生んだ。
[出典:”A story of oppression: freedom of expression, minorities, sexual harassment law and offence” <The Religion Factor>University of groningen]
【5】国際社会からの復興支援の「受け皿」となるガザの行政機構をいかに構築するか?日本には「平和外交」の確かな実績がある

[出典:「自衛隊を活かす会」東京外国語大学の伊勢崎賢治名誉教授]
話を本題に戻そう。「自衛隊を活かす会」のシンポジウムで伊勢崎氏は2023年10月7日に起きたガザ戦争を「10.7」とすることから口火を切った。「このガザ・イスラエル戦争はいきなりハマスが引き起こしたわけではなく、連綿と続く戦争の中の一つの『奇襲攻撃』として認識されるべきだ。人質の安否を憂い停戦を求めるイスラエル国内世論の高まりに乗じて戦争を続けたいベンジャミン・ネタニヤフ政権の印象操作によるハマスの『絶対悪視』と『停戦』を謳う国連安保理決議案に頑なに拒否権を行使する米国のジョー・バイデン政権、その政府の根拠にある。米国はガザ戦争が周辺国が介入する地域紛争に発展する恐れを明確にしている。既にヒズボラを擁するレバノンとの国境上の戦闘は激化し、イスラエルと関係のある船籍を攻撃しているイエメンの親イラン武装組織に対する『航行の自由』を掲げる米国は紅海での多国籍軍を主導せざるを得ない。フーシー派グローバルサウスと共に周辺のアラブ諸国では広くイスラエルを包囲する世論が高まり、米国内の世論もイスラエルへの軍事供与の是非を次期大統領選を視野に大きく政局化しつつある」と解説した。
その上で「ガザ戦争の終結とは一体何か?」実務家としての逸案を伊勢崎氏は語り始めた。「現在も続く『停戦交渉』は『人質』と『捕虜』の交換を原則としているので、いつか種切れになるだろう。戦闘終結後のガザ統治をどうするか?というビジョン交渉の下で構築すべきだ。まず、イスラエル軍のガザ全面撤退を目指す。同時にハマスにも譲歩を求める。それこそが『武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)』である。ハマスが自ら整然と武装解除した後、武器や弾薬のガザ流入の防止を国際社会が保障措置する必要がある。目指すべき交渉の最終的な帰着点に向けて説得できるのは米国以外にしか利害はない。そして仲裁する権限を与えられた国際監視団を創設する。想定するのは国際平和維持軍の定番になっている多国籍の非武装の軍人で構成される『軍事監視団(military Observer)』だ」と。「ハマスは休戦交渉を仲介してきたカタールを中心にアラブ諸国が主導し、それを国連が承認する『国際監視団』ならば条件を飲む可能性はある」との希望的先見を述べた。
一方で伊勢崎氏は「問題はイスラエルだ。アラブ諸国や周辺国に難色を示すだろう。その場合、グローバルサウスに主導させ、地域政治からより独立した国々で構成する案が考えられる。国際社会からの復興支援の受け皿となるガザの行政機構をいかに構築するか?国際社会の支援を得るためには既に国連でオブザーバーの位置を得ているパレスチナ自治政府を前に立てなくてはならない。米国にも同様の思惑がある。だが、その場合にハマスとパレスチナ自治政府の関係が問題になる。ハマスは2006年にパレスチナ国政選挙でヨルダン川西岸及びガザ地区で民主的第一党に選ばれた正当な「政体(Polity)」だ。パレスチナ自治政府の腐敗や汚職に対する不満が燻る土壌の中から生まれたのが「ハマス」だった。民主主義に則った「政体」の経験がある「ハマス」は単なる「テロリスト」ではなく「対話可能」であり「停戦交渉」の余地がある」と現実的提案を示した。
結語として「10.7ガザ戦争でも他の親米国家、特に日本の役割があるはずだ。日本の自衛隊にはネパールでの『武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)』監視の実績がある。かつて『パレスチナ解放機構(PLO)』議長だった故・ヤーセル・アラファト氏は西側先進諸国から『テロリスト』扱いされていても、日本はアラファト氏を日本に招聘した。また、フィリピン政府と同国南部ミンダナオ島の反政府武装勢力モロ・イスラム解放戦線(MILF)が、2016年にイスラム系住民らによる新たな自治政府設立を目指す和平工作を『国際開発機構(JICA)』故・緒方貞子理事長が先頭に立って主導した時もあった。日本にはそうした『平和外交』の実績があることから、世界の中で平和貢献の核となる素質があると信じている」と期待を込めた。
【6】「殺傷武器は外す」という決断のなさこそ「人道的軍縮キャンペーン」が有効に関与できないワケ

[出典:「緑の党」「武器取引反対ネットワーク(NAJAT)」杉原浩司 代表]
前出の杉原氏のご専門である「武器禁輸」のテーマについても言及があったことから同様に別途・他ウェビナーでの発言を続けて引く。
「今パレスチナでイスラエルが引き起こしているジェノサイドで、AIを使った兵器が使用されている。標的を自動的に割り出して、残虐な空爆をすることに利用されている。キラーロボット反対キャンペーンは、現実にAIが戦争犯罪に使用されているこの問題について、声を上げるべきではないか。
ガザ、西岸に対する『ジェノサイド』『民族浄化』と呼ばれるほどの大虐殺を行っているイスラエルに対して、米国やドイツが武器を輸出しているのに、『武器貿易条約(ATT)』が全く歯止めになっていないという現実がそこにある。
日本で『武器貿易条約』の締約国会合が開催された際に軍縮大使を務めていた高見澤将林(タカミザワ・ノブシゲ)氏は、殺傷武器輸出解禁に向けた与党密室協議の中で、「かつての『防衛装備移転三原則』策定時の議論では、殺傷武器を外すことは想定していなかった」旨を証言した。議事概要すら示さない密室での伝聞に基づいて、搭載できなかった殺傷武器の搭載に道が開かれてしまった。
「人道的軍縮」に日本政府は積極的な顔をしつつ、結局のところ自国の殺傷武器輸出の動きを加速させている。そこで高見澤氏が役割を果たしていることに見られるように、武器輸出や軍拡に対して『人道的軍縮』キャンペーンが全く有効に関与できていないという問題が私たちの目の前にある」
第212回国会「安全保障委員会」(令和5年11月9日)自由民主党 鬼木 誠 衆議院議員の質疑などから同問題を提起する。2022年度から23年度にかけて岸田政権の安全保障委員会は「防衛予算」の増強「安保関連三文書」「防衛生産基盤強化法」の制定を行った。「日英」、「日・豪円滑化協定(RAA)」ともに締結し日本の防衛力強化を図ってきた。

[出典:第三国への直接輸出「歯止めが必要」自・公に“隔たり”『次期戦闘機』輸出めぐり協議【報道ステーション】(2024年2月21日)]
そのうちの「安保関連3文書」の一つ「防衛力整備計画」に導入予定だった主なスタンドミサイルの中にある米国製トマホークがある。さらに2023年12月に設置された「GCAP政府間機関(GIGO)」の下に「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)」計画を一元的に管理する、日英伊の3カ国共同で次期戦闘機を開発している。2035年頃に退役を開始する「F2戦闘機」の後継機となる予定だ。2024年2月21日に初となる自民・公明政調会長会談が開かれ、協議されたが両党には見解の相違が見られる。次期戦闘機の開発とは無関係な第三国への輸出を認めるか否かについてだ。
公明党の山口那津男代表は「次期戦闘機を第三国に輸出することを無期限でやるとなれば、高度な殺傷能力を持った兵器を第三国、すなわち世界中に出すとあらゆる武器について輸出できることに繋がるのではないか?現制度では認められていない第三国への直接輸出の実施には歯止めが必要だ」と懸念を示した。
[出典:第三国への直接輸出「歯止めが必要」自・公に“隔たり”『次期戦闘機』輸出めぐり協議【報道ステーション】(2024年2月21日)]
前出の柳澤氏は「次期戦闘機の開発完成品輸出」まで昨年末で決め打ちしてしまった岸田政権の現状に対し「今までは部品しか輸出しなかったが(次期戦闘機の)完成品を出せるようにする。米国がウクライナ軍事支援疲弊して在庫を使い尽くしているから、日本のような同盟国で賄って欲しいという米側の要望に呼応したものだ。これは防衛産業ビジネスの『儲け』というより、むしろ動機は政治的な利益の問題を意味する。『日本には米国本土だけでなく第三国のグアムに駐留する米軍にも輸出して欲しい』あるいはウクライナならまだしも『米国が軍事支援していた在庫が尽きたから台湾にも同様の開発完成兵器を日本からも輸出してほしい』などの米国の思惑に先見を持つべきだ。このリスクを注視していくと、防衛産業(軍産複合体:コングロマリット)だけを悪視して戦争の原因だという見方を私は取らない。むしろ国民を動員する国政と世論の中で起きる自国に対する戦争の根本原因に問題を見出す。これらの開発完成兵器輸出の流れこそが、日本の戦争に巻き込まれるリスクを負う成否を見極める必要があるだろう」と新たな戦争を生み得る軍拡への道に警鐘を鳴らした。(文責・飛立)

[出典:ウクライナ、ガザ戦争、イラク戦争から20年拙記事からコラージュ作成]
<結び>「言論弾圧」と「ヒミツ」が横行したら…「軍靴の音」がする前触れ
2002年当時、筆者は「個人情報保護法廃案運動」に加わっており、会議に毎週参加し、「皆さんが個人情報保護法にこれだけ反対しても、民意がついてこないのは、きちんと報道被害の問題と向き合っていないからではありませんか?」と「分をわきまえず発言」して同意した方々の議論の呼び水に少しはなれたのではないかと。報道関係者の内部に入って一石を投じることでもしないと報道被害は解決しないという問題意識から取材していた。
「個人情報保護法」とは「人権擁護法案」「青少年有害社会環境対策基本法」を含めて「メディア規制関連三法」と呼ばれ、「言論弾圧」であり、「表現の自由」規制だと市民運動、リベラル系ジャーナリスト、有識者らがデモをして声を上げていた。
それから時が経ち、突如として出てきたのが2013年の「特定秘密保護法」だった。当時、東京新聞の半田 茂記者が「不可解な『防衛秘密』漏えい事件」を寄稿していた。本書から抜粋する。
「陸上自衛隊がイラクに派遣される時に、僕がスクープした武器使用基準の記事(『東京新聞』2004年1月1日付)があります。もちろんどういう筋から情報を入手したかは言えませんが、きわめて正確な記事であることは間違いなくて、元日から防衛庁がてんやわんやになりましたが、警務隊が動くようなことにはなりませんでした。
では、読売と朝日・僕の記事の違いは何か?煎じ詰めると、アメリカが絡むかどうかということです。朝日や僕の記事はアメリカと直接の関係はありませんが、読売の記事の元になっている情報は、アメリカからもたらされた情報でした。これが日本政府にとっての「セーフ」と「アウト」の基準ではないかと思います」
筆者は当時、本書評「秘密保護法で封殺される『知る権利』と『表現の自由』」[「秘密保護法は何をねらうか 何が秘密?それは秘密です」清水雅彦・䑓 宏士・半田 茂共著<高文研>]<bukupe>を自腹で執筆して知った。

「十分な審議を尽くさず、猛反対の民意を無視してまでの強行採決を急いだ安倍政権情勢の裏には、米国とあらかじめ年内立法化の密約を交わしていたためではないかとの報道も一部見られた。その米国では2013年に「スノーデン事件」が起こった。当時ロシアに亡命中の元米中央情報局(CIA)職員だったエドワード・スノーデン氏が米国家安全保障局(NASA)の個人情報収集問題を暴露した事件。この事件を契機として、英国ではガーディアン紙が英国諜報機関による承認を受けてNSAと水面下で秘密取引を交わしていた米国が、英国市民の携帯やインターネット、E mailの情報を不正に分析し、収集データ蓄積していたことが分かったと報じるなど、米、英、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ間では「ファイブ・アイズ」と呼ばれる情報共有同盟が既に結ばれていた。
元NYタイムズの記者でフリージャーナリストのクリス・ヘッジズ氏(ピューリッツァー賞受賞)は、「ハモンド、スノーデン、マニング、アサンジ、ブラウンのような人物なしに報道の自由はない」と指摘している。」
さらに依頼を受けて書評「軍靴の音が聞こえる戦争準備のための秘密保全法制」[「秘密法で戦争準備・原発推進―市民が主権者である社会を否定する秘密保護法」海渡 雄一著<創史社>]も自腹で執筆した。本書から抜粋する。
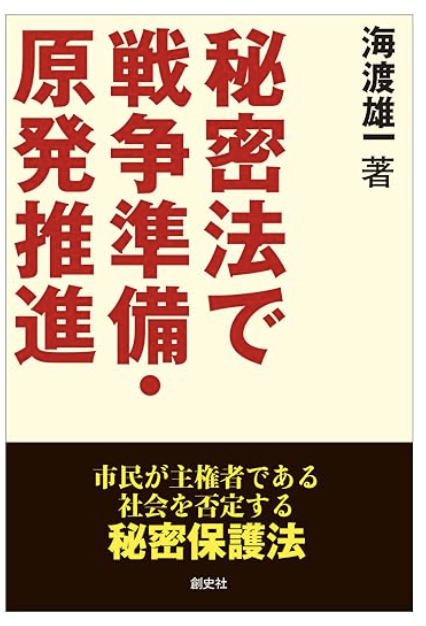
「本書では自民党日本国憲法改正案の本質にも迫り、国防軍と集団的自衛権公認によって戦争ができる国家へと作り変えられると熱を込めて綴られているが、現に2013年12月23日には南スーダンPKOに参加していた陸上自衛隊の銃弾1万発を国連経由で韓国軍に提供する方針を固め、武器輸出三原則(当時)の例外扱いとした他、2014年1月8日には自民党運動方針の最終案の原案から、安倍首相が行った靖国参拝について「不戦の誓いと平和国家の理念を貫くことを決意し」との表現が削除された。近年の一連の日本政府の動向からは、軍靴の音が間近に迫った軍事国家へと転落していく序章に思えることに著者は魂を込めて訴追の声を上げ続けているのである。」

[筆者拙記事コラージュ作成]
上記にもあるように、2013年の「特定秘密保護法」、2014年に「集団的自衛権」閣議決定。そしてあの長きにわたる2015年「安保法制」(安倍政権時)と市民運動、リベラル系ジャーナリスト、有識者、NGO関係者らが「束」になって「国民的闘い」を挑んでいたものである。筆者は「安保法制」の闘いでボツの原稿を段ボール2箱分ほど書き続け熱意が認められて<寄稿>私の提言「自衛隊に代わる平和貢献を」<国際開発ジャーナル(2016年12月号)>に至ったが、発表した後に「修正的護憲派」に思想を移行した。3.11以降、自衛隊による災害救出活動は市民の注目を集めてきた。自衛隊の存在を認めない日本の市民など、もはやいないだろう。だからこそ筆者は今だに「自衛隊を活かす会」と関わりがある。
第一次安倍政権で武器輸出が解禁され「非核三原則」から「防衛装備移転三原則」に名称を変え乗り換えた。当初は「攻撃殺傷能力」のある兵器開発は「防衛装備移転三原則」が歯止めになり不可能だった。ところが現在の岸田文雄内閣に政権交代しても「安保法制」の時と違って2022年12月17日にあっさりと「安保関連三文書」が閣議決定し、その改定に伴う条件付き武器輸出を認める上に「防衛装備移転三原則」まで運用指針を見直すことになった。それを踏まえて今般の「次機戦闘機」輸出問題が浮上してきたのだ。
日本が東南アジア(ASEAN)など売りつけたい諸国でも「次期戦闘機」のほか、「スタンド・オフ・ミサイル技術」なども開発すべきだと有識者会議で提言されてきた。岸田文雄政権が「兵器開発」のタガを徐々に外していき、「先端兵器」の開発や輸出を推し進める道へと猪突猛進していく近未来が危惧されてきた。
2024年に入ると米国で予てから開発されてきた最大速度マッハ250kmで空爆できる「極超音速兵器」まで岸田政権は米側と「軍拡」に合意してしまった。

[筆者拙記事コラージュ作成]
遡ること2022年9月に外務省は「開発協力大綱(ODA)」の「改定」を発表した。件の「安保関連3文書」の改定に合わせ「外交と防衛の両輪」でやるという政府施政方針を示した。すなわち、安全保障や経済安保のためのODAを戦略的に活用した。外務省が武器供与を無償譲渡し、非軍事原則を無かったことにすることで、「戦争しない国」という意味で世界からも「ふつうの国」では無かった日本は、従来憲法による平和主義=非軍事原則と見做され、それに基づき国際協力の現場で働く日本のNGO団体が信頼を勝ち得て「身の安全」を生んでいることを「日本国際ボランティアセンター(JVC)」の今井高樹代表理事は国際協力の現場の皮膚感覚から感じてきた。今井氏はアフガニスタンを一例に挙げ「日本のNGOは欧米と違って軍事注入していないから欧米のNGOがタリバンから襲撃されたりすることが頻繁にあっても、日本人は違う」との認識から、身の安全がそこで保証されてきたからだ」と強調した上で「武器の無償供与は国際NGO職員の信頼を失い、命の危機に晒すのではないか」と糾弾したのだ。
[出典:【安保関連3文書】外務省が他国軍に武器供与?!日本のODAから「『非』軍事原則」が消える当事者置き去りの大転換 飛立知希 著<ガジェット通信連載JP>(2023年2月22日)]
筆者はその岸田版「戦争法制(War Bill)」とでも言おうか「安保関連3文書」との新たな闘いとして、さらに2023年早々に「抑止力の限界」などを議論する「平和構想提言会議」が創設された動向も捉え「安全関連三文書」反対キャンペーンを張ってきた。同会議の共同座長でもある、学習院大学の青井未帆教授(憲法学)は、憲法及び国際法の範疇で行動計画を策定。「東アジアに敵を作らない共通の安全保障の促進と市民が参画する多国間の安全保障」を提言してきた。
2008年4月17日には名古屋高等裁判所がイラクでの航空自衛隊の輸送活動につき、「米国の『武力行使と一体化』したものだ。日本自らが憲法9条1項が禁じた『武力行使』をしたと言わざるを得ない」として憲法9条1項違反の判決を出している。
筆者が青井氏の講演会で「北朝鮮や中国などの敵性国家が日本領土に届くミサイル・核攻撃を行う脅威を想定して政府は『集団的自衛権』を後付けではなく初めから行使する政策方針を打ち出している。仮にそうなれば日本を攻撃してもいいという『口実』を敵性国家に与えるようになってしまう。その上、誤った舵取りをして国民をミスリードしたら、米国と共にモニタリングをし、『自動参戦条項』含め、攻撃機能使用可能国家になってしまうのではないか?過去の戦時下と同じ過ちを繰り返さないためにも日本の国防なりヒューマンセキュリティーの課題を包括した在り方を模索すべきではないか?では、どうするか?」と「自動参戦条項」について質すと、青井氏は「その始まりの恐れがあまり知られていないことがポイントなのだと思う。まるで日本にはまだ決定権があるかの如く思われている。実際には日本の裁量は小さいという点がかなり大きなポイントであり、だからこそ在日米軍基地使用の法体系として『事前協議』が効いてくるという話に繋がっていくのではないか。在日米軍基地を特に『東アジア地域での紛争』に対しても使えなければ、アメリカも作戦には踏み切れない」と述べた。
その上で「専守防衛」の定義における受動的な防衛戦略の姿勢における『憲法の精神』とは、権力に縛りをかける最高法規の『前文』と『平和主義』を斬り捨て真逆の意味にし、「武力行使」可能との政府憲法解釈論の限界を直視せねばならない。「他衛権」のために「先制攻撃」を現行憲法上でもなし得るものにした」
[出典:【安保関連3文書】 防衛力強化隠蔽「お題目としての憲法」悪用 飛立知希 著<ガジェット通信連載JP>(2023年2月4日)]
反戦の声をあげる口を封じられる「言論弾圧」と権力の「ヒミツ」が横行したら…それこそが忍び寄る「軍靴の足音」が聞こえる前兆なのだ。
日本には国宝「憲法9条」があっても実質的に既に「戦争加担国」でさらなる「軍拡」へ暴走している。その「歯止め」となる「言論の自由の力」を伝えることこそが「『非戦』の国際世論」を高め、このまま日本人が海外の戦争リスクに巻き込まれていかないよう筆者は「平和へ続く国民的議論」を深めることで最大の暴力である戦争に楔を打つ一介の書き手でありたい。

