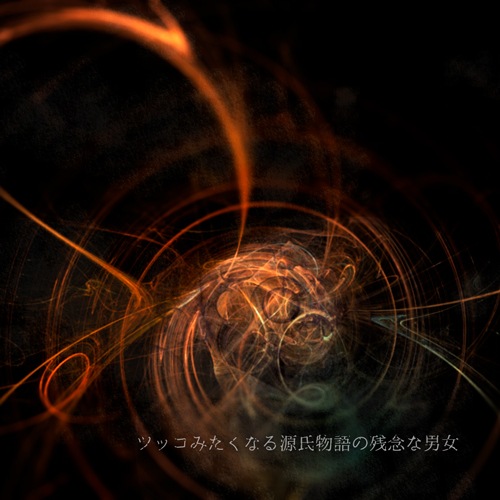
「悲しみを祈りにかえて」妻の切なる願い
六条院の女性方との合奏で見事な腕前を発揮した紫の上。どこをとっても非の打ち所がない彼女も、今年37歳の大厄の年。源氏は何やら得体の知れない不安を感じます。
「私は幼い頃からとても恵まれた幸せな人生を送ってきたが、一方では誰よりも悲しい目にもあってきた。母や祖母とは早くに別れ、その後もさまざまな悲しい別れに立ち会った。でもその悲しみのおかげで、今日まで生き延びているのだと思う」。
更に、京を離れた数年以外は、紫の上に”実家暮らしのような”安心できる生活を約束してきたと言い、思いがけず女三の宮との結婚があったが、それも結果的にはあなたへの愛情を再確認するための過程でしかなかったと訴えます。だいぶ都合のいい解釈ですね。
それでも、紫の上には源氏の言いたいことがよくわかりました。「おっしゃるように、身内に縁の薄い私には身に余る幸せな日々でした。そして殿と同じく、私もずっと心に堪えかねた悲しみを祈りにかえて、生きているような気がします」。
まだ言いたいことがあるけど……という感じで、彼女は少し間を置き「本当のことを言うと、どうも先が短いような気がするの。だからどうか出家のお許しを下さい」。しかし源氏はとんでもないと、請け合いません。
「自分の浮気心のせいで…」過去の女性遍歴を反省
話をそらそうと、源氏は過去の女性遍歴を語り出します。「年をとるにつれて、優しく賢く落ち着いた……理想的な女性はなかなかいないと思うようになった。
夕霧の母・葵の上とは若すぎる結婚をして、お互いに意地の張り合いばかりで終わってしまった。私も悪い所があったが、あちらは真面目で堅苦しく柔軟さに欠けた。しっかりしていて立派だったが、夫婦としてはやりづらい人だった」。彼女のこの性質は、息子・夕霧にしっかり遺伝しているような気がします。
「秋好中宮の母・六条御息所は稀に見る才媛で、大変優れた人だったが、恋人としてはなかなか厄介な人だった。プライドが高くて繊細で、思いつめる性格だから一緒にいても気が休まらない。
若かった私は、年上の彼女の前でいつも背伸びをし、それに疲れて足が遠のいた。でもその後も葵祭の車争いで彼女にひどい恥をかかせてしまい、そのことを深く恨んでいたのを知って、更に恐ろしくなって……」。
更に源氏は幾人かの女性たちのことを語り「でも結局は、私の往来の浮気性がこうした因縁を作って、残念な結果を生み出している」とまとめます。わかってるけど、どうしようもない女癖です。
このあと2人は明石の上が素晴らしいことなどを話して終わり、源氏は「宮のところへ上手に弾けたお祝いを言いに行こう」と寝殿へ。宮は自分のせいで紫の上が悩んでいるとは思いもよらず、今日も独りでお稽古に励んでいます。
源氏はその熱心さが微笑ましく「琴も疲れているから、今日はもうお休みだ。よく教えた先生にもご褒美を下さいね」。そういって琴をどけて寝台に入ります。
嫉妬に憂愁、孤独…ひとり絶望を噛み締めた夜
一方、紫の上は、女房の物語の読み聞かせを聞いていました。宮の輿入れ以降、源氏のいない夜はこんな風に過ごすのが習慣になっていました。物語にはいろいろな男と女が出てきますが、すったもんだが繰り広げられても結局、最後に主人公とヒロインが結ばれておしまいです。
紫の上は「いろんな展開をしたところで、どのお話も結末は決まっているらしい。でも私はそうなれなかった。殿のただひとりの妻として居続けることができなかった。
確かに私の人生は恵まれていたと思う。でもその半面、逃れられない嫉妬や憂愁に付きまとわれ続けていかなくてはならないのだわ。これからもずっと……」。
誰もがうらやむ光源氏の妻としての人生は、常に彼の浮気心に苦しみ、新しい女性の登場に怯える日々でもありました。そして、彼女はそれを呪いではなく祈りに変えて、今日まで過ごしてきたのです。
しかしこの期に及んで「こんなにいい暮らしが出来て幸せだっただろう?俺を置いて出家するな」という源氏は、彼女の心の内をどうやっても知りえない。夫婦として、家族として、長く一緒に暮らしてきたのに……。
たとえどんなに仲が良くても、お互いを理解し合っていると思っていても、別個の人間である以上、100%わかり合えるということはありえない。
誰もが知っているけれど気づきたくない真実を、彼女はこの夜、改めて噛み締めたのでした。この人生の重い命題こそ、源氏物語を普遍のものとする大きな理由の一つだと思います。
やるせない気持ちで横になった紫の上は、その夜に突然発作を起こし、ひどく苦しみます。慌てた女房たちが源氏に知らせようとするのを「いけない。せっかく宮のところへ行かれたのだから」と制止。源氏が事態を知ったのは、すっかり朝になってからでした。
胸の痛みと高熱!必死の看病も効果ない謎の病
「急にどうしたのか」と、大慌てで戻った源氏が触れると、紫の上の体は火のように熱い。これは大変だと寝食も忘れて、つきっきりで彼女の看病に明け暮れます。その甲斐もなく、紫の上は食事も摂れず寝たきりになってしまいました。点滴とかないですからね……。
具体的にどういう病気とも言えず、ただひたすら苦しみあえぐ紫の上。特に胸は時折激しく痛み、高熱も引きません。
源氏は僧侶たちを大勢呼び集めて加持祈祷をさせ、なんとしても愛する妻を病魔から救おうと必死です。当然ながら、朱雀院の50歳のお祝いも延期。あちらから逆に「どうかお大事に」と丁寧なお見舞いを頂いてしまう始末でした。
看病も祈祷もむなしく、紫の上の容態は快復しないまま一ヶ月ほどが過ぎました。何をやっても結果が出ない! 源氏の嘆きは言い尽くせません。場所を変えたら好転するかもと、元の住まいの二条院へ移動させることにします。
六条院は上を下への大騒ぎで、多くの人が紫の上を慕って二条院行きを希望。お腹の大きな明石の女御も付き添い、父娘で看病を交代します。また、源氏の真の息子である冷泉院や夕霧も、父の心痛を思いやり、彼女のための祈祷や手伝いをするのでした。
紫の上は、少し意識のはっきりしているときにはものを言うこともありました。源氏には「どうか出家のお許しを。もう死ぬのならわずかな間でも出家して、救いを得たいのです」。しかし、こんな病状で出家なんてありえないと、源氏はまったく聞きいれません。
産み月も近い女御には「こんなところで、大事なお体に差し障りがあっては」と心配し、可愛い孫宮たちを見ては「大きくなるのを見たかった。みんな小さいから、おばあちゃんのことは忘れてしまうでしょうね」。大好きな母がそんな悲しいことを言うのに堪えられず、女御もひどく泣きます。
「縁起でもない。たとえどんな運命でも、心の持ちようで違ってくるものなのだ。ポジティブで大らかな心構えの人は長生きするじゃないか」。源氏は精神論まで持ち出して、僧侶たちにも檄を飛ばし、一層熱心に祈祷に励むよう頼みます。
しかし紫の上は弱っていくばかり。少し落ち着いた日が数日あるかと思えば、また悪化……というのを繰り返し、床離れできません。源氏は「もう治らないのか?助からないのだろうか?」と、嘆き悲しみ、他のことは一切忘れて側についていました。
いろいろ残念なところのある源氏ですが、ここでの必死の看病は真剣そのもので、胸を打ちます。重い病に倒れた人とその家族の苦闘は、医学が発達した今も変わらぬリアリティを持って迫ってきます。
晴れて結婚も「コレジャナイ」片思いをこじらせた青年の今
誰もが紫の上のために右往左往する中、六条院に取り残されたのは女三の宮。まるで火が消えたような邸内に、今や歌舞音曲が流れることはありません。誰もが「紫の上こそが六条院の華だった」と思い知ります。ここにきて宮のお飾りぶりがいよいよ露呈したわけです。
源氏は看病を理由に二条院を離れず、宮のもとへ泊まることはおろか、様子見の訪問すら忘れています。この隙を狙っていた男がひとり。あの柏木です。
柏木も年月のうちに出世し、ついに結婚もしました。「どうしても皇女さまがいい」と粘ったおかげで、父の頭の中将の応援もあり、女三の宮のすぐ上の姉・女二の宮と結婚することが出来たのです。
この女二の宮は、三の宮の次に朱雀院が可愛がっていた皇女でした。が、母の身分が更衣と低い。皇族出身の三の宮とはかなり差がつきますが、かえってそれなら気安いかと、お嫁さんにもらうことにしたのです。同じプリンセスとは言え、母親の身分で扱いが大きく変わる時代です。
女二の宮は皇女らしい気品のある、素敵な女性でしたが、何と言っても妹の方を思いつめて長い上、仮にも姿を見ている柏木は「コレジャナイ」感が増すばかり。当然愛情もわき起こらず、悪い噂が立たない程度におもてなししているだけ。いわゆる仮面夫婦というやつです。
あれだけ「宮を飾り物にしている」と源氏を批難した男が、自分の妻に迎えた人に同じことをしているのはなんとも皮肉で、片腹痛いですね。形だけの夫婦関係を続けながらなお、女三の宮を思いきれない柏木は、小侍従を呼び出してある相談を持ちかけます。
簡単なあらすじや相関図はこちらのサイトが参考になります。
3分で読む源氏物語 http://genji.choice8989.info/index.html
源氏物語の世界 再編集版 http://www.genji-monogatari.net/

