
GSOMIA破棄見直し 河野防衛相が再度要請©️NHK政治マガジン
2019年11月17日、タイで主催されている東南アジア諸国連合(ASEAN)拡大国防相会議(ADMMプラス)に河野太郎防衛相が出席した。同日、韓国の鄭景斗(チョン・ギョンドゥ)国防相との日韓2+2防衛相会談も主催された。また15日、米国のマーク・エスパー国防長官は、韓国の文在寅大統領に今月23日で失効期限を迎える、日韓の「軍事情報包括保護協定(GSOMIA)」の打開策を見出すため秋波を送ったばかりだ。
その直後の17日、日米韓防衛相三ヶ国会談が開かれた。
この席でエスパー国防長官は今月末に予定していた米韓合同軍事演習の延期を発表。日韓には互いに「歩み寄り」を促した。しかし日韓間の隔たりは平行線のままでGSOMIA失効までのカウントダウンを迎える絶望的な状況だ。
金正恩氏 4月「施政演説」で掲げた「忍耐」切れがトランプ氏三行半の決め手か?

2019年の北朝鮮による発射©️Yahoo!News
北朝鮮は、今年7月末の日韓対立が深まった当時から短距離弾道ミサイル発射実験を連発し始めた。韓国は「飛翔体」という表現に抑え、「宥和」路線を保とうとしたが、当初の北朝鮮の連続した「短距離ミサイル発射実験」は米韓軍事合同演習に反対の意思を示す向きが強かった。
だが、8月11日から20日まで行われた後も北朝鮮は8月末、9月中旬、10月初頭の新型SLBM発射実験を成功と自画自賛し、同月末にも北朝鮮は短距離弾道ミサイル実験を続けてきた。これを受けた国連安保理ではドイツ、ベルギー、ポーランドと常任理事国のフランスと英国の五カ国が大量破壊兵器の即時放棄を迫った。北朝鮮は「米国が敵対政策からの完全で不可逆性のある撤退」を承諾しなければ、非核交渉の席には戻らないと語った。日本を射程圏内とする短距離弾道ミサイル「ノドン」の更なる技術開発と増産も続いているという。
今年4月12日、金正恩朝鮮労働党委員長が最高人民会議で行った「施政演説」による「今年末まで忍耐心を持って米国の勇断を待つが、前回のような好機を得るのは困難だろう」。これが北朝鮮が年末まで忍耐を続けると見せかけ、内実は「並進路線」を復活させるかのような匂いを醸し出しているのを見抜けない米国に判断を見誤らせたことで、金正恩の小賢しい外交手腕が米国に優ったかもしれないと今までは錯覚されてきた。
トランプ政権にとっては激しい後悔の念を避けるべく、緊張状態の低下していた際に取り付けた合意におそらく違反している「開発兵器」を持ち込んだやり手の掟破りの独裁者だ、と米国側に金氏は映っていた。しかし、8月20日に米韓合同軍事演習が終わったことで金氏は対話という「(トランプ氏の)お気に入りに流れを戻せる」と楽観視してきた。
だが、短距離弾道ミサイルの連発という自身の掲げたはずの「忍耐」切れが、ついにトランプ氏を苛立たせ「9月末会談見送り」と突き放された金氏の鼻っ柱と打算的な挑発外交は打ち砕かれた格好だ。
今年6月末の第三回板門店米朝首脳会談より以前から、金正恩氏がトランプ氏と会談する前には、常に中国の習近平国家主席と会談して習氏に知恵を付けられてから臨むという戦略をとり続けてきた北朝鮮ペースを崩さねばならない。
南北対話を拒否している北朝鮮にも日本にも追い詰められている韓国をどうするべきか。半導体競争から始まったが徴用工を巡る問題を引き合いに出してきた韓国には、GSOMIA破棄でこじれた日韓関係に容易に米国は手を出すべきではない。それはこのモラル・インペリメントの問題に韓国側が紐づけてきた懲用工問題には歴史的な労働条件の不満を持続的に解決することでしか和解することはできないからだ。
米国が果たすべき役割というのは、安全保障協力の重要性を再確認するのに日米韓首脳会談を開催し、日韓関係の安定性を支援する環境こそを整備すべきではないかというのが筆者の9月までの見立てだった。
しかし「核軍縮」問題に取り組む上で「抑止力」と「被曝者運動・核廃絶」という切り離せない矛盾した普遍的なテーゼを理解するために、あえて基礎研究としてロジカルに整理した解説をここに上梓することにした。
被爆国でありながら日本が核兵器禁止条約に批准できない本質的な理由
今年11月1日、国連総会第一委員会(軍縮)は日本が主導する核兵器廃絶決議案を26年間連続で148カ国の賛成多数で採択した。賛成は米国など核保有国と各同盟国ら26カ国が棄権し、昨年同様、ロシア、中国、北朝鮮、シリアの四カ国が反対するなど去年に比べ12カ国が減った。
一方で、核兵器禁止条約に対しては日本は去年に引き続き反対した。なぜ、被爆国の日本が「核廃絶」を主導する一方で、核兵器禁止条約という被爆者運動の賜物には批准できないのか?この矛盾した難題がいつまでも解けないことには「軍縮」と「抑止力」の関係性を理解することができない。
日本という被爆国に生まれた一介の書き手として理由を筆者なりに解説する。殊、トランプ政権に交代してからは、2017年2月10日の安倍・トランプ日米共同声明で「核及び通常戦力の双方によるあらゆる種類の米軍の軍事力を使った日本の防衛」を行うと明記してしまったことがそもそもの発端である。
この米国の「拡大抑止」政策に依拠しきっていることが被爆国であるはずの日本を「核兵器禁止条約」に批准できない国にしているどころか、「核保有国と非核保有国との橋渡し役」などと上辺だけの言葉を並べることしかできなくさえさせてしまっていた。
今年11月の核兵器廃絶決議案の場でも「未来志向の対話」という文言だけが俎上に上がり、肝心の米露ポストINF離脱を受けた核削減への言及や中東大量破壊兵器非核化構想の記述もなかった。
さらに言えば、原爆投下直後は「世界法廷」という非人道的な「絶対悪」としての核兵器を憲法とジュネーブ条約・第一追加議定書などの国際人道法で断罪する場ならばあった、という史実がある。だが人類は未だ「地球裁判所」のようなものを創設していない。
米国による「抑止力」に通常兵器の面でも核兵器の側面からも甘んじ続けてきた日本は、歴史を振り返ってみても米政府の顔色を常に伺い、たいてい反対の声が上がると圧力をかけるなどして政策論争の場ではあたかもなかったかのごとく見做されてきた。

[筆者撮影・サーロー節子さん 記者会見(2018年12月6日)]
2017年の「核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)」がノーベル平和賞授賞の際に演説したカナダ在住の被爆者、サーロー節子さん(86)が昨年12月5日に自民党の岸田文雄政調会長に面会し「岸田さんが『もっとサーローさん達のアイデアをこれからもお受けしたい』と開襟して話ができたこと」が最も感触を掴めたとする一方、もう一人の面会者であった西村康稔内閣官房副長官が「政府としては市民を守る必要があるから核兵器を持つという選択肢もあり得る」という政府見解を示したことに対し「73年も証言活動を続けてきましたが、広島と長崎の被爆体験を最も理解しているはずの日本政府が『核禁条約』の交渉にさえ参加せず、さらにこの見解まで抱くのは被爆者として絶対に許してはならない。受け入れられない」と繰り返し何度も訴えたことを強調した(2018年12月6日、都内・PEACE BOAT事務所での記者会見・筆者取材)。
このように、日本政府は常に上辺では「核保有国と非核保有国の橋渡し役を」と口上しておきながら「敵基地攻撃能力」である「核武装論」というオプションを常に持ち続けていることが北東アジアの安全保障上の本音だと政府高官の口から語られた言葉から事実だと分かるのである。予てから北大西洋条約機構(NATO)の抑止力としてニュークリアシェアリングの問題と米国と同盟を結ぶアジア太平洋の諸国の「核の傘」抑止力の課題が国家安全保障の問題とは複雑に結びついていることこそが真の原因である。
核軍縮問題の本質はこの「抑止力」をいかに理解し、それと逆行する核廃絶を目指すヒバクシャの運動と日本中に逆巻く反核感情のうねりをいかに理解するかにこそある。
防衛研究所特別研究官の高橋杉雄政策シュミレーション室長執筆の「日本:世界で最も厳しい安全保障環境下での核抑止」の結論部分をまず引き、「抑止力の」第一義的な基礎理解の助けとする。
「核兵器の使用の可能性を極限まで小さくするために核抑止力が現実として必要であり、かつそれが機能しているという現実を受け入れた上で、核抑止力の論理と両立する軍縮の論理を提示していくことが日本の核軍縮の専門家に求められ」ている。
この簡潔明瞭な定義を頭にインプットした上で、外務省の今西靖治軍備管理軍縮課長が示した「核兵器の廃絶に向けた様々なアプローチー核軍縮を進める共通基盤としての透明性および検証可能性」から得た日本政府側の考える軍縮の総論的課題を思い起こす。国際法学でいう法乖離論という「法の欠缺」がある。分かりやすく言えば、「核兵器を禁止し廃絶する」ことが混在した効果的措置の特定と追求が見られる。
そして簡潔に言ってしまえば、核廃絶のために「(不可逆、検証可能、かつ)透明な」追加的措置が必要だと2017年国連総会に提出された「多国間核軍縮交渉の前進」決議における「透明性」の追求。そして米国が主導する「核軍縮検証のための国際パートナーシップ(IPNDV)」が牽引する今日の「検証」の履行というものが政府側に立った総論としては公式見解であった。
「ウォーファイティング」を前提としない「抑止力」の新時代 「相互確証経済破壊」
しかし、今西氏の総論から導き出される「法乖離論」と「核軍縮の透明性と検証」の追求と履行を基礎研究の第二義的理解としても、それを遥かに凌駕する新たなる時代の幕開けを告げる論考がここに存在する。
長崎核廃絶研究センター(RECNA)編集国際学術雑誌『平和と核軍縮』“Journal for Peace and Nuclear Disarmament”第2巻1号(2019年7月号)に寄稿された英文博士論文、国際地政学研究所の柳澤協二所長著「米朝首脳会談と新たな安全保障思考の可能性」。略称「柳澤論文」である。

国際地政学研究所の柳澤協二所長著「米朝首脳会談と新たな安全保障思考の可能性」国際学術雑誌『平和と核軍縮』“Journal for Peace and Nuclear Disarmament”第2巻1号(2019年7月号)
その要旨を抜粋した後にポイントだけ詳細に見ていく。
“著者は(中略)北朝鮮非核化協議を事例にとって、安全保障措置としての核抑止はもはや効果的でない時代に入りつつあると論じる。冷戦期と違い、国際社会はより相互の接続性が増し、各国経済は他国経済に依存するようになってきている。戦争を通じて他国を破壊することは、自らの経済的基盤の一部を破壊することに等しい。したがって、現下の問題は、米国あるいは中国が核報復を行うことによって世界を物理的に破壊してしまうことではなく、グローバル経済が機能不全に陥る「相互確証経済破壊」の可能性にあると言えよう。しかし、戦争というオプションがもはや実現可能ではないことが明らかになっても、日本は依然として米国の拡大抑止政策に固執している。北朝鮮の核兵器を、協議とインセンティブの供与によって取り除くことができれば、抑止以外のアプローチが機能すると実証することができよう”。
この論文はベトナムのハノイで主催された第二回米朝首脳会談前に執筆されたものと思われ、その点においては筆者の国際情勢の後追いウォッチと核問題を専門とするジャーナリストである共同通信の太田昌克編集委員が南北の非武装地帯でサプライズとして行われた第三回米朝首脳会談を取材し分析したポリシーペーパー「北朝鮮非核化の現状と課題」による視点の獲得と併せて考察する際に斬新な論考としての真の価値を発揮する。
トランプ氏は今、「ウクライナ・スキャンダル」で弾劾公聴会の民主党を筆頭とする議会と米ジャーナリズムの激しい追及に遭っている。
しかし、9月に解任されたジョン・ボルトン大統領補佐官(国家安全保障担当)はトランプ政権在任期間中、喩えるなら人間鉄球のように北朝鮮の外交政策を破壊し尽くしてきた。
今年2月、ボルトン氏が同行したベトナムはハノイでの第二回米朝首脳会談においても経済的な圧力をかけて威嚇し、米国に全ての制裁を撤廃して欲しければ、北の無条件即時の完全なる非核化をしろと頭ごなしに檄を飛ばす。だが、ボルトン氏が予測していた通り、その提案は拒絶された。結果として米国は機会を失することとなる。完全なる非核化へ道半ばの限られた合意形成が生まれるとしたら、うち固められていたであろう重要性が。
金正恩にとっても、ジョージ・W・ブッシュ政権期の閣僚だったボルトン氏が「リビヤモデル」を提唱していたことは脅威だった。ムアンマル・アル・カダフィ大佐がそうであったように、彼自身が大量破壊兵器開発計画を離れた地で取引し始めてから7年も経たないうちに、血塗られた運命が待ち受けていたからだ。ボルトン氏が辞任後、金氏もそれを予見して自分が生き延びるためにもボルトン氏の発言一つ一つが脅威に聞こえていたという解釈を吐露している。
そのボルトン氏はもはや国家安全保障を担う車輪の一部品ではなくなったことで活き活きとしてウクライナ問題で弾劾のドラマを繰り広げる大統領に潜在的に持っていた牙を向ける旗振り役になろうとしている。政権内で20年以上も北朝鮮の核の脅威を減退させることに従事してきた曝露本まで用意しているほどだ。
筆者は爆破したはずの東倉里の実験場が見事に再建されているのを衛星画像で確認した。
同じハノイの地を踏んだ者でも、太田氏は根拠1として①プルトニウム②高濃縮ウラン③トリチウムという核開発3点セットが製造できる重要拠点の寧辺の原子炉を、また根拠2となる元ロスアラモス米国立研究所のシグフリード・ヘッカー所長への単独インタビューを通じて「他にも一つか二つ施設があり、そこで濃縮試験を行ったが故に寧辺の施設を整備したというのが私の結論だ」と言質を用いて、これほど大規模かつ短期間に建造されたということは、(その前段に)他に研究用の濃縮施設があるに違いないという子ブッシュ政権時の国務省高官の証言で裏付け、核技術の常識からして他のプロトタイプ施設での度重なる実験や試運転なしには不可能だという論証を導き出している。それらから北朝鮮のウラン濃縮能力は相当なレベルに達していると見るべきであり、だからこそ6.12のシンガポールにおける第一回米朝首脳会談で「交渉を続ける間は(寧辺の)核活動を停止しろ」と釘を刺すべきだったという中心的主張を繰り返し展開している。
皮肉なことに前述のボルトン氏の辞任を受けて、10月5日にスウェーデンのストックホルムで米朝実務者協議が実現した。だが、キーマンの徐薫院長を筆頭に韓国国家情報院筋によれば決裂したとの報が入ってきている。しかしその第二ラウンドが遅かれ早かれ12月中には開かれるという。10月6日には中朝国交樹立70周年を記念して習氏と金氏両首脳が祝電を交換した。米国のトランプ大統領との第四回会談が年末年始に行われるのではないかとの可能性も浮上。
これまでの金氏の対米外交戦略から、訪中カードを再び切る可能性も出てきた。
既に述べてきた国際情勢を俯瞰した時に、優れた光を投げかけてくるのが「柳澤論文」である。北朝鮮の連射してくる短距離ミサイルを「もし撃ち漏らしてしまったら」と2018年2月14日の第193回国会予算委員会で安倍晋三首相が答弁した「北朝鮮が弾道ミサイルを発射された際、それを共同で日本を防衛する国家は米国だけであります。そしてもしミサイルを撃ちもらしてしまったら、それに対して報復できる唯一の国家というのも米国であるわけです。(北朝鮮が)このことを肝に命じておかないと、この抑止力は破綻し、暴走する可能性も捨てきれない」と、安倍首相の発言というのは抑止力の概念を要約するとより力強い報復でさえ脅威によって反撃される攻撃を意図しているものだと分かるとした上で、「日本に着弾するかもしれないというシナリオを除外するわけには行かない」と柳澤氏は問題提起する。
日本政府が米国の核の傘の下に拡大抑止こそが安全保障の自信を持てる政策の根拠だと考えていたその理由とは、もし冷戦期に二つの核の超大国のうち一国がー米国か旧ソヴィエトかがー他方を攻撃したら、同盟国は核報復の潜在的なリスクを生んで報復したことだろう。この想定とは、同盟国に対するものでさえ軍事侵略の抑止力の結果になるはずだったと言うものだ。
冷戦期におけるリベラリズムと共産主義、全体主義の間の内紛が存在の様式間の内紛であった。双方の側が強い信念を持ち、「私は全体主義の下に自分の自由を失う以上にむしろ死を意味しただろう」そして「我々は資本主義によって私利私欲のために使われることを自分たち自身に認めることはできない」と互いの体制を正当化するというイデオロギーが起こす衝突が戦争の定義であり、核兵器による抑止力が働く時代だった。
今日、2国間において絶対的なイデオロギーの内紛というものは存在しない。世界は経済的な競争によって制御されるようになった。国境を超えた巨額の資本と国家の経済ごとに他国に依存している。戦争を通じたもう一つの国家の破壊とは、今やそれ自体の経済的根拠の一部を破壊することに相当するものなのだ。
今日あるのは「スチヂーヂスの罠」による絶対的権力を超えた米中間の可能性ある戦争を超えた関心事である。貿易と開発された技術をめぐる競争が増し続ける。しかしながら、この内紛の真の性質とは、経済的かつ技術的な優位性を争うものであり、その優勢を失いうる可能性を熟考するので、米国が経験する恐怖が悪化させる要因になっている。この問題は戦争という武力による実力行使では解決することはできない。
国際地政学研究所の柳澤協二所長著「米朝首脳会談と新たな安全保障思考の可能性」国際学術雑誌『平和と核軍縮』“Journal for Peace and Nuclear Disarmament”第2巻1号(2019年7月号)
そしてこの論文で柳澤氏が行き着いた一つの答えが経済語彙を用いた以下の概念だった。
最近の関心事はそれ故に米中の核報復による世界の物理的破壊ではなく、むしろ「相互確証経済破壊」というグローバル経済が機能不全に陥ることにある。
戦争を通じたそれ自体の破壊のリスクで核兵器を装備した敵対者を非自発的に破壊する内戦の解決のための動機付けの欠如にある。
もはや主要な核保有国では核兵器が戦争の動機にはならない。例えば、ロシアによるクリミア併合や中国による南シナ海の島嶼の掌握、米国に遂行されたイラク戦争は防げなかった。
小中国にとって核保有国の核の傘の下に置かれていないことが実際の問題だった。このような核兵器の存在はこれらの場合において戦争を防ぐことにはならない。
我々の現在の状況においてインセンティブを申し出たり、交渉するのに、力が主要な国家間を継続的に移っていくような明白な戦略は未だ存在しない。
国際地政学研究所の柳澤協二所長著「米朝首脳会談と新たな安全保障思考の可能性」国際学術雑誌『平和と核軍縮』“Journal for Peace and Nuclear Disarmament”第2巻1号(2019年7月号)
と「抑止力」の代わりになるものとして「インセンティブ」を挙げている。北朝鮮の場合は体制保証(CVIG)と経済力の改善だ。そして残る問題として
イデオロギーで支持されているテロリストと呼ばれる武装集団は支配ではなく、殺害を目的としている。彼らは国家や人民や文化や領土を持たない。つまり核攻撃を通じて何の失うものもないので懸念することもない。それ故に軍事力でテロリズムを止めることは困難だ。
今日、偉大なるグローバルリスクとは核兵器の可能性がある。そしてそれはもはや国家間の戦争の道具として使用されることはない。テロリストの手に核兵器が渡ったら、その時それは抑止力ではなく、殺害の手段として使われる。
テロリストはNPT条約に決して批准しないだろう。
核兵器を開発し、行使するテロリストの脅威とは、国際社会の問題を維持するだろう。単に国家間ではなく、人間同士の間の内紛も、もし我々が暴力と破壊の全ての形を根絶したいと願うなら、解決されねばならない。それを終焉に導く上でも、核兵器や軍事力は解決しない。
核による抑止力から動く新たなアプローチとは、このように必要なものだと考察できる“
と柳澤氏は新たなテロリズムの脅威の再定義を行う、日本は今や、米国のための戦場が日本の領土に関する問題になるであろうことを見越して核兵器や通常戦力が使われるべきか否か考察する必要がある。日米間で軍事的な結びつきがタイトなものとなったにも拘らず、両国はそんな戦争に相当する損害に悩み苦しむことにはならないだろう。
安全保障の確証ある政策の根拠は今や疑問に満ちたものになっている。我々はこの状況を抑止力の必要性として受け入れるべきか?我々のプライオリティーが日本を撃つミサイルを防ぐべきことにあるのか?日本は究極的な抑止力としての核兵器に依存し続けるべきか?代わりに我々は、核兵器が使われなくなり、存在する必要性もないものにする世界を生み出す目的を持つべきではないのだろうか?
国際地政学研究所の柳澤協二所長著「米朝首脳会談と新たな安全保障思考の可能性」国際学術雑誌『平和と核軍縮』“Journal for Peace and Nuclear Disarmament”第2巻1号(2019年7月号)
とあくまで読者に投げかけてこの「柳澤論文」は筆を置いている。
「The Diplomat」アンキット・パンダ上級編集者が斬る!金正恩核戦略抑止論

New U.S. Missiles in Asia Could Increase the North Korean Nuclear Threat ©️Foreign Policy
今年11月15日、軍縮・科学技術センターで米国科学者連盟(FAS)防衛態勢プロジェクトのアンキット・パンダ客員上級研究員の基調講演会が主催された。パンダ氏は2020年8月に「北朝鮮の核戦力と核戦略」に関する著書を刊行予定だという。筆者は不覚にも体調管理の不備で、この講演会への出席を逃してしまった。
「核武装した北朝鮮の核抑止」をテーマとしていただけに、アジア・太平洋の外交メディアとして名高い「The Diplomat」の上級編集者としても度々、大手マスメディアに買われ、引用されるパンダ氏の発言や分析、考察を近著述からも引証してこのアジェンダについて考察してみたい。
パンダ氏は今回来日して前日の木曜にも催しをこなしている。驚くべきことにその多忙なスケジュールの中、「Foreign Policy」(2019年11月14日)にも記事を発表。
中でも見逃せないパンダ氏の視点とは、米政府直系の軍事シンクタンク「ランド・コーポレーション」が公式に掲げているように、「米国の概念上のグローバル戦力分割戦略図」で第二プライオリティーの「インド・太平洋地域」の一つ「台湾」を中国からの弾道ミサイル射程圏内国防要衝と位置付けている点にも斬り込んでいることだ。
ポストINF時代に注目すべきアジア太平洋地域の軍縮とは、中国の東海岸から2000マイル近くに所在するグアムの米領土に配備された米国のポストINF太平洋戦域における明白な好敵手国、すなわち中国をめぐる国防において、日本のような米国の同盟国と深刻な相談を始めるまでは、米国防省の計画では少なくとも1800から2400マイルの射程距離能力を持った、少なくとも新たに一つのポストINF弾道ミサイルーグアムからの危機に対し、「台湾」周辺戦域の作戦全体像のある中国東部の安全保障を保つための理想的なシステムーを間も無く開発する計画がある。それは滞空時間丁度20分間で同時に平壌の空爆能力をも併せ持ったミサイルだ。
New U.S. Missiles in Asia Could Increase the North Korean Nuclear Threat ©️Foreign Policy
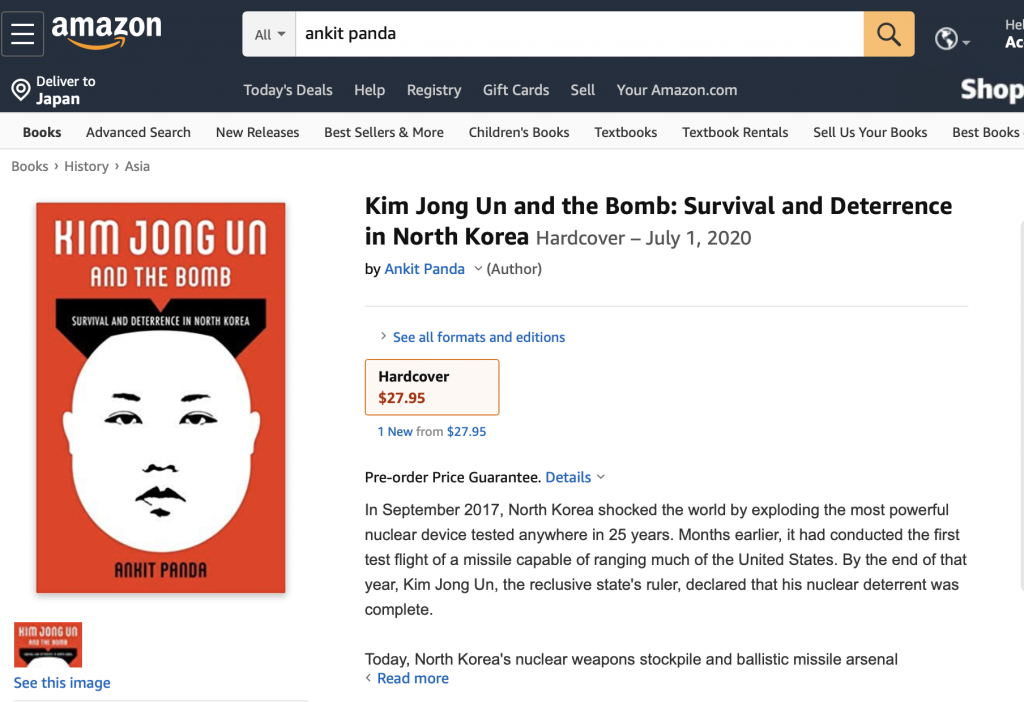
Kim Jong Un and the Bomb:Survival and Deterrence in North Korea by Ankit Panda
その上で北朝鮮については「『完全かつ検証可能で不可逆的な体制保証(CVIG)』には改めて金正恩体制の核兵器へのレバレッジ(融資・投資)を必要とする」ものだという経済の語彙で説明づけている。同じく「相互確証経済破壊」という経済の語彙で現代の新たなる幕開けの抑止力に代わる時代の処方箋を読み解いた「柳沢論文」に近しくも非なるところが部分的に見受けられる。
数年間、北朝鮮は特に米国の通常戦力B1B爆撃機と核能力を保有するB -2ステルス爆撃機が所謂、朝鮮半島近くの爆撃機の保証と抑止任務を管理しているとして、猫が逆毛を立てるように苛立ちと怒りを抑え切れずに示してきた。
北朝鮮外務省の広報官は、米国が繰り返す核実験を引き合いに、平壌が米国から脅威に晒され続けていると説明した。その戦略的ミサイル防衛システム、ICBM、SLBM、そして2019年度の米本土のミサイル防衛システムを含むそのような一連の行動を指している。
原子力潜水艦から放たれる核攻撃のSLBMなのか、米通常兵器のB-1B爆撃機なのかも含み、北朝鮮は通常戦力か核兵器かの見分けがつき難いという特徴を持っている。国防力にかけては脆弱な国家だという定評は予てから変わらない。故に金氏は、ミサイル迎撃技術か、あるいは戦略的早期警戒可能性のある、グアムからの指令発出脅威偵察能力を北朝鮮軍部が開発へ「投資する」ことを望むことができない。
2017年11月に「核能力完成」宣言を行い核武装国家となってから、北朝鮮との核抑止の関係性は壊れやすく、まだ日が浅い。そして危険性の高いものだ。かつて米国が熟考しなければならなかったのはロシアと中国間の核能力の安定性であった。しかし今や北朝鮮こそが懸念事項に入れなければならない第三の敵対国である。
New U.S. Missiles in Asia Could Increase the North Korean Nuclear Threat ©️Foreign Policy
すなわち、北朝鮮には武装した核はあっても、攻撃の標的とされた際にそれを国防の予防的措置として上手く使えず、誤爆・誤使用する可能性が高いというのである。
これまで軍縮問題の本質である「抑止力」の基礎研究の第一義的、第二義的な意味を押さえ、その応用編である「柳澤論文」まで知見を高めてきた。
さらにアンキット・パンダ氏というアジア太平洋における核戦略とミサイル防衛の専門家の見解も考察に入れて情勢分析の一助としてきた。
それを踏まえた上で筆者は現時点における次の自分なりの答えに到達した。
行き着いた私見的答えとトライアルシナリオ
前述の「相互確証経済破壊」という経済への相互依存の新たな概念だが、一見それに相反する核軍縮の国際法学的な「法乖離論」の中で、被爆者運動というものが忌避し難く、「非政府主導型の世界を創る」というコンセプトに立って啓発を促していくということと平和教育を担保していきながら、軍縮というものに市民社会全体でコミットメントをしていく。グラスルートの力を借りる。たとえばICANの川崎哲国際運営委員は常日頃から「核兵器は絶対悪である」という言われ方をされる。それに対して、京都大学大学院の浅田正彦教授(国際法学)は「核軍縮は絶対善とは限らない。なぜかというと軍縮はその目的を国際安全保障政策とし、軍縮措置によって安全保障の根幹が危険に晒されたら、外交がその解決策に成り代わるものだからである」という記述の仕方をされる。そのため、市民社会が軍縮というモダニティーを促すという意味合いで「非政府主導型の世界を創る」というところで「武器を持たない自衛隊を創る」とのコンセプトから「専守防衛」との整合性を図っていくという考えを持つのも一案ではないか?
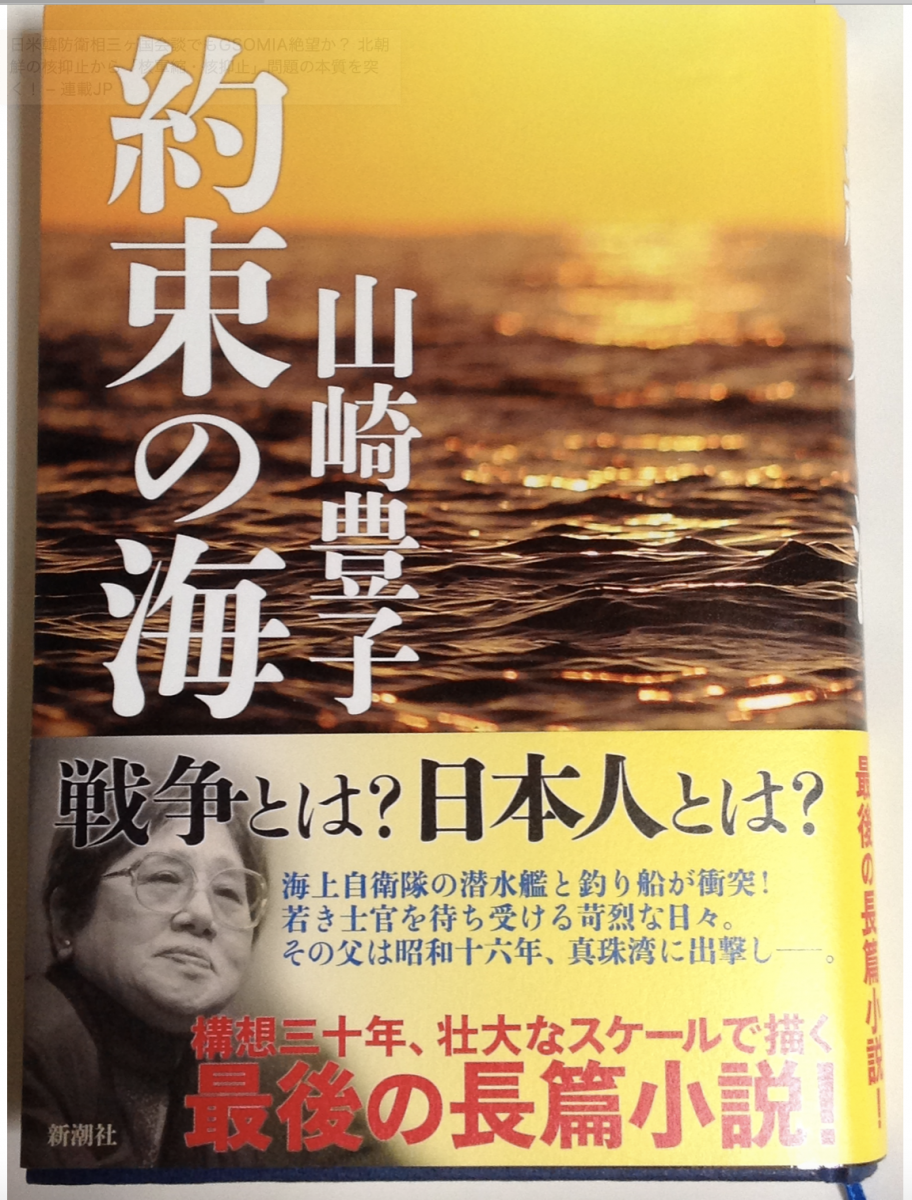
「約束の海」©️山崎豊子
「武器を持たない自衛隊を創る」という案は、日本一の社会派作家と激賞された故山崎豊子氏の遺作「約束の海」の幻の第3部からきている。この作品が連載されていた「週刊新潮」編集部が取材班を組み、第3部目に「中国という仮想敵国と東シナ海での紛争を想定し、鎮魂の海に武器を持たない軍隊を模索する」というシナリオ設定になっていた。取材班はその過程で柳澤協二氏や東京新聞の半田滋氏ら他錚々たる顔ぶれの関係者への取材を既に終えていたようだ。
山崎豊子氏亡き今、その仮想敵国とは中国だけではなく、北朝鮮を加えた中朝に成り代わる国際情勢に移行しつつある。そしてその核たる問題とは、「北朝鮮の非核化」だ。
太田氏は先に挙げたRECNAのポリシーペーパーで最新の第三回板門店会談の課題分析として、次の4回目の米朝首脳会談では「シンガポール共同声明にあるエンドステートをより具体化した新たな首脳間合意文書の策定を急ぐ。」とし、両首脳が署名して非核化の「初期的措置」に着手、具現化するプロセスと並行して「ロードマップ」を実務者間で策定。寧辺以外の核施設を完全申告させることに非核化協議の力点を傾注すべきだ。その上で、上記の措置を北朝鮮が履行しなかった場合、イランの核合意「包括的共同作業計画(JCPOA)」にある「スナップバック」機能を参照し、もし一旦解除していれば、その時は制裁措置を自動的に再発動できるシステムを米中露を中心に構築すべきだ、と政策提言する。
太田氏が長年フォローしてきた非核化交渉史における米朝間の「信頼関係の完全なる欠如」に対し、信頼醸成を優先させる具体的な約束事をいずれか一方が違反した場合、懲罰を確実に加えるメカニズムを担保すべきではないかと強調する。
筆者は「鎮魂の海からサイバー戦へと主戦場を移しているのが現代」ではないか?との問題意識があった。

サイバー完全兵器ー世界の覇権が一気に変わる ©️デービッド・サンガー
重い経済制裁を課されている国家にとって、自己資金をかき集めるための手段を編み出すのは死活問題である。そのためか、北朝鮮は殊、サイバーハッキングの腕が立つ。バングラデッシュのグラミン銀行だけではなく、ベトナムのティエンフォン銀行もポーランド、ベネズエラ、エストニア、チリ、ブラジル、メキシコの中央銀行当局者も狙われた。韓国のビットコイン取引所もハッキングしたことで、「北朝鮮は今、サイバー犯罪で国家の運営資金を荒稼ぎする史上初めての国になっているのかもしれない」とNYタイムズのデービッド・サンガー記者は自著「サイバー完全兵器―世界の覇権が一気に変わる」の中で指摘する。あの第4次米朝核危機が苛烈を極めた2017年も、北朝鮮は韓国の国防統合データセンターから侵入し、米国の「斬首作戦」や韓国の「キルチェーン」を含む正式名称「作戦計画5015」なる軍事文書へのハッキングも成功させていた。敵の動揺を誘い作戦計画を一から書き直させることを狙いとし、北朝鮮政府はわざと「デジタル潜伏工作員」の重要インフラ侵入を気付かせようとした証拠まであった。
これに引き続き、ランサムウェア「ワナクライ(WannaCry)」が世界中に広まった。
NSAがハッカー集団「シャドー・ブローカーズ」のハッキングを受けた一件で、マイクロソフトウェアの脆弱性を突く「エターナル・ブルー」というプログラムが盗まれ、それがワナクライの感染拡大に利用されたのだ。
74カ国を襲ったワナクライはイギリス国家サイバーセキュリティー・センター(NCSC)の緊急対応部門でさえも何も知らなかったと答えている。イギリス政府通信本部(GCHQ)もマイクロソフトもワナクライの前になす術がなかったのだ。
「ワナクライ」は被害の一部として他国の政府機関を含み、「サイバー攻撃の国際法タリンマニュアル2.0」規則4「主権侵害(Sovereignty Rule4-Violation of Sovereignty)に基づき、「国家は、他国の主権を侵害するサイバー行動を行ってはならない」と定めるが、そのコメンタリーによれば、本質的な政府の機能の行使に必要なシステムやデータに悪影響を及ぼす遠隔サイバー攻撃が、この規則違反に該当するとされている。
また国際法上、サイバーテロ犯を「私人」と見做した場合であっても、「私人」による行為の国家行為への帰属性の問題を上記の北朝鮮の実例に当てはめて見れば、「国家責任条文」第8条「国により指揮または命令された行為」に該当するものとして1999年タジッチ事件上訴裁判部本部案判決で、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)は、武装集団のような階級的構造を持つ集団において、その行為が国家に帰属するには特定行為の指示は不要であり、集団に対する全般的支配(overall control)(財政支援・装備供与だけでなく軍事行動の組織、調整、計画への介入)で事足りるとする「ジェノサイド条約適用事件」判例(ICJ本案判決2007年2月26日)が参考になる。
上記を踏まえ稚拙かもしれないが、従来の軍縮の枠組みからすると型破りな新たなアプローチを不意に考案していた。
宇宙法・サイバー法はまだそこまで進展していない。規制対象が限定的である。北朝鮮という主権国家から搬出できない核兵器のデメリットをオルタナティブするものとして、国際法の法規範や判決以外の主権国家に対する抜け道が多い宇宙・サイバー関連法分野の進出と議論を闊達化させて権力に縛りをかける憲法の役割にも似た監視機関の効力をかけ続ける。非国家武装勢力への対処として、「違法性阻却事由か?あるいは合法行為か?」例えば…
【仮シナリオ】
(ア)A国<中国>領域内に所在しないハッカー<北朝鮮ハッカー集団ラザルス(仮)>がC国<日本>のインフラを使ってB国<米国>に対する遠隔サイバー攻撃を行う場合。
折しも時代は2020年東京五輪パラリンピックを迎えるまで1年を切った頃。国家安全保障に北東アジアの「抑止力戦略」と2018年12月から自衛隊に編成された「クロス・ドメイン」政策のサイバー・宇宙部隊の精鋭が揃っている。中朝による策謀が五輪の背後、ブラックマーケット上のエクスプロイド・コード争奪戦を繰り広げる中、スポーツの祭典が栄華を極める。北朝鮮の国家規模ハッカー集団ラザルス(仮)が日本のITインフラを使ったことで日米同盟が窮地に。さらにサイバー戦でも憲法9条が日本の必要最小限の自衛権や防衛力を阻害する影響を与えていた。米中間の国家機密コードを狙ったサイバー戦争の激突。情報収集、警戒監視、偵察といった「違法ではない」スプーフィングなどで、ペンタゴンの機密IPルーターネットワークや在日米軍のインフラ相互攻撃が幕を開ける。サイバー戦略本部の置かれた各局メディアは、とあるソーシャルファームの市民メディアによるこの事件の末端を暴いたスクープから国家全体を巻き込んだ一大スキャンダルを暴き出す取材攻勢をかけ全容を明らかに国家の膿を出すのだった。
太田氏にも柳澤氏にも山崎豊子氏にもはるか遠く及ばない稚拙な議論ではあるものの、年配者に気後れして挑戦しなければ何らの成長もない。「核廃絶」と「専守防衛」を目指すこれからの日本に思いを馳せ、憲法9条と戦時国際法の整合性を取ること。それが日本を担う次世代に渡された重要なバトンではないだろうか。

