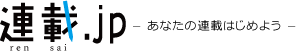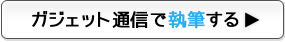世界中で発生し、長期化している紛争の数々。
報道で取り上げられる機会の多いウクライナとイスラエル・ガザ以外でも、世界のいたるところで今なお続く。
2023年現在、世界34ヶ国で59もの国家間の紛争があり(75もの非国家間の紛争も)、
4億7,300万人の子どもたち(世界の子ども人口の約5 人に1人)が紛争地に暮らす。
こうした紛争を背景に、子どもたちにとって大切な「教育」への攻撃も多発している。

【画像】スーダンの西ダルフール州で、人びとが避難していた学校の跡地は2度にわたり破壊された
では、紛争下での教育の保護、学校の軍事利用禁止などを規定する「学校保護宣言」という、国際的な指針をご存じだろうか?
同宣言は、2015年に行われたノルウェー・オスロ会合にて多国間協議で策定され、現在では紛争当事国を含む世界121もの国々が支持を表明。
その一方、 G7諸国の中で賛同していないのは日本のみという驚きの状況があるのだ。
子ども支援NGO(公益社団法人)のセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、教育協力NGOネットワークやヒューマン・ライツ・ウォッチら協力団体とともに、
「学校保護宣言」への日本政府の賛同を求め、署名活動を中心とした啓発キャンペーンを、2025年4月から展開している。

【画像】ガザ南部のハンユニスで壊された学校
宣言賛同国の取り組み事例―アフガニスタ等で、学校や大学の軍事利用の報告件数が半減
宣言の策定日(2015.5.29)から10年を迎える前の5月27日、
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは協力団体とともに、メディア向けの説明会を行い、筆者もオンラインで参加した。
同NGOのアドボカシー部 松山晶さんから、紛争当事国の教育の実状や、宣言の概要、賛同国の取り組み事例が紹介された。
教育を攻撃から守るための国際的な指針「学校保護宣言」は、国際法の範囲内で、すべての紛争当事者・関係者の行動変容を促すものとされる。
賛同国に対して、ガイドラインの内容を国内政策等に反映・実施すること、教育への攻撃のモニタリング・報告、被害者支援、加害者の訴追、教育施設の再建支援など、紛争影響下でも教育を継続するための取り組みを求めている。
そのガイドラインには、
「軍事利用の目的で、開校中の学校を使用することの禁止」「武装紛争下における学校の意図的破壊の禁止」「敵が軍事目的で使用している学校への攻撃をする際、事前警告をするなど代替手段の検討義務」といった6つが挙げられている。
では、同宣言に賛同している国の取り組みにはどういったものがあるのか。
セーブ・ザ・チルドレンの資料によると、2015-2016年に賛同し、その2年間に教育施設の軍事利用が報告されていたアフガニスタンイラクなど13の国々では、2015年から2020年の間で、学校や大学の軍事利用の報告件数が半減。
2017年以降、国連平和維持活動(PKO)による学校・大学の軍事利用は確認されていないそう。
また、デンマーク、エクアドル、ニュージーランド、スイスでは、軍事マニュアルを改訂し、 学校の軍事利用を明確に禁止する規定を含めたなど、政策レベルでも明確な動きがあるようだ。
「学校保護宣言キャンペーン」の概要

セーブ・ザ・チルドレンが事務局となり、協力団体・賛同団体と展開している、
日本政府に「学校保護宣言」への賛同を求める署名キャンペーンについても、説明会で紹介された。
まず、署名は、オンライン署名サイトとして有名な「Change.org(チェンジ・ドット・オーグ)」と、「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」のWEBサイト「あすのコンパス」で受け付けている。
各ページでは宣言に関する分かりやすい解説が掲載されているので、まずは宣言について学びたい人にはチェックしていただきたい。
4/8にキャンペーンが開始され、5/27時点で既に8000人を超す署名が集まっているとのこと。
署名の提出先は外務省、防衛省、人道支援・国際政策に関わる議員連盟・国会議員などが挙げられている。
今後、宣言の認知・理解の向上を目的としたイベントも計画しているようなので、署名だけではない関わり方も出てきそうだ。
最後に、署名のなかの一つの声を紹介する。
「私たち高校生は将来のために一生懸命勉強しています。 それは世界全体で同じことです。子どもの未来を軍事利用で奪わないで下さい。(15歳・東京都在住)」
日本にいると、なかなか見えづらく、現実的でない世界の紛争の数々。
しかし目を背けず、まずは“声をあげる”ことから始めてみてはいかがだろうか。