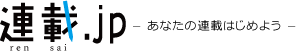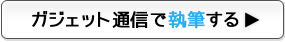秋は結婚式シーズンですね。僕も先週、お友達の結婚式に参加してきました。よく「新しい出会いがあるかも…」なんて言いますが、あれってどうやってそういう「出会い」に発展するんですかね?僕には分かりません。さておき。
お昼の情報番組で「結婚式に親から資金援助を受けた?」というような話題がありまして。
結婚は自分達が愛し合って2人で決めた結果なので結婚式も当然に2人が主体で行うもの、つまりは親に援助してもらうのは甘えでしかない。自力でできないならやるべきではない。
というのが多勢を占めている様子でした。
ところで、結婚式をした方、出席した方ならご存知かと思いますが、式場での案内は「○○、××御両家」というのが大半です。
もしその形を取るのであれば家長は親父さんなので、主催は2人というよりむしろ両家の親父さんで然るべきであって、もし当事者という事にこだわるのであれば親父さんもお袋さんもお客様席にいないとおかしい。
何れににしても親父さんの援助があったほうが無いよりは呼ばれる方にすれば金銭的なレベルで満足度は上乗せされるのは間違いないので、
そこら辺深く考えもせず招待状に親父さんの名前書いてカツカツの式やったら見方によっては「あそこの親父はあんな寂しい結婚式しかだしてやれない」みたいな事になる可能性だって否定できません。
結婚式での援助の可否についていつも思うのは
「2人にとって最初の大きな買い物」
なのか
「両親から子どもへの最後の贈り物」
なのかというところ。結婚式をどちらに捉えるかで援助のアリナシは決まるんじゃないでしょうか。
どちらの考え方もアリだと思うのですが、この手の話題でしばしば問題になるのが、「もう片方」のイメージすらもたぬままに「甘えるな」だ「何が悪いの?」と考え、自分が必ずしも真っ当だと思いそうでないものを非難すること。
特に結婚は自分の家の常識だけでなく、今まで全く異なる道を歩んできたパートナーの家の常識も絡んでくるもの。お互いの事が大好きで、何でも知っていると思っていても、住む土地も環境も違う二人。必ずしもその「常識」が一致しているとは限りません。
どちらも考え方自体は間違ってはいないから、援助受けてなきゃあ「2人はちゃんと自立してやれます」で御披露目すればいいし、
逆に援助受けたから恥ずかしいとか思う必要もなくて「何十年後には俺らも子どもに出してやるから。ありがとうねパパ」くらいでむしろ金出してくれる余裕のある親父さんを誇りに思っていればいいと思います。
これからながーく暮らしていくための第一歩。お互いを尊重して、気持よく結婚式が迎えられるといいですね。
画像:写真素材 押成(http://www.ashinari.com/)より引用